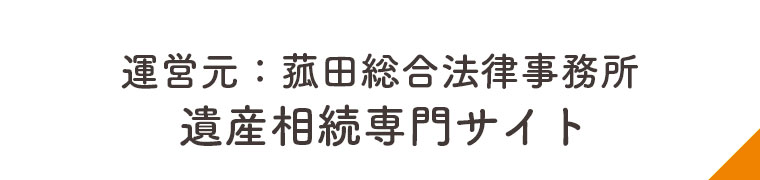特別受益って何?|特別受益がある場合の相続について弁護士が解説
- HOME
- お悩み別コラム
- 相続で揉めている・預貯金の使い込み・生前贈与
- 特別受益って何?|特別受益がある場合の相続について弁護士が解説
動画でわかりやすく解説!
特定の相続人だけが、被相続人(亡くなられた方)から贈与や援助を受けていた場合、そのまま遺産分割が行われると、他の相続人との間に不公平が生じてしまいます。
自分以外の相続人に被相続人からの贈与や援助が疑われていた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
1.特別受益とは
特別受益とは、複数人の相続人がいる中で、特定の相続人が被相続人から特別な利益を受けていた場合の受益分を指します。
特別受益は大きく、「遺贈」「死因贈与」「生前贈与」の3つに分類されます。
まず「遺贈」とは、被相続人の遺言に基づいて財産を贈与する事を指します。
被相続人(贈与者)の意思のみで相続を決めることができます。
そのため、受取人は放棄することができます。
また、遺贈であれば相続人以外の人が財産を受け取ることも可能です。
次に「死因贈与」とは、被相続人が死亡したことを条件として行われる贈与をいいます。
死因贈与の場合には、被相続人(贈与者)は、相続する人から事前に承諾を得ておく必要があります。
死因贈与の場合には相続放棄ができない為、注意が必要です。
「生前贈与」については、不動産の無償使用や生活費の資金援助、学費及び婚資(持参金、結納金)といったものが考えられます。
以上、特別受益に該当しうる項目を挙げましたが、たとえ項目に該当した場合においても、一律に特別受益と認められるわけではありません。
特別受益かどうかの判断は、遺贈などが行われた経緯やその金額、被相続人の生活状況や社会的地位など様々な要素を総合的に考慮して判断されることになります。
2.どんなケースが特別受益に該当するか
前述したように、特別受益とは、相続開始前に特定の相続人が被相続人から受け取った金銭や物的利益を指します。
次に挙げる具体例は、いずれも相続分の調整対象となる代表的なケースです。
どのような贈与や扶養が「特別受益」として認められるのか、一つずつ見ていきましょう。
2-1.現金贈与
被相続人が相続開始前に特定の相続人に数百万円から数千万円の現金を贈与した場合、通帳の振込記録や贈与契約書が証拠となり、相続分調整の対象になるケースが多いです。
2-2.不動産贈与
被相続人が相続開始前に土地や建物を特定の相続人に無償で贈与した場合、その不動産の時価相当額が特別受益とみなされます。
登記簿謄本の譲渡履歴や贈与契約書を証拠として提出し、相続分から当該評価額を控除します。
2-3.有価証券・金融資産の贈与
株式や投資信託、債券などの金融商品を生前に譲渡したケースも対象です。
証券会社の受渡簿や取引報告書を基に、相続開始日時点の時価を算定し、特別受益額として相続分の調整に組み込みます。
2-4.扶養的贈与(生活費・学費・医療費の負担)
被相続人の生活維持や教育、治療目的で継続的に生活費や学費、医療費を立て替えた場合、その総額が扶養的贈与として特別受益に該当します。
領収書や医療明細、学費納付書などを集め、実費総額を相続分から差し引きます。
補足:上記に該当したら、必ず特別受益が認められるのか?
上記いずれの場合でも、上記があったからといって絶対に特別受益が認められるわけではないことには留意が必要です。
たとえ現金贈与や不動産贈与、金融資産譲渡、扶養的立替があったとしても、以下の条件を満たさなければ「特別受益」として認められない場合があります。
- 1.贈与の意思表示が明確か
- 2.対価が一切支払われていないか
- 3.家族間の通常扶養を超えたものか
- 4.相続開始との時間的関係
- 5.相続人間の合意または裁判所判断
単なる「贈与のつもりだった」「将来の相続分前渡しのつもりだった」という当事者間の口約束だけでは不十分で、贈与契約書や贈与契約の記録が必要です。
一部でも相当額を返還していたり、報酬や見返りがあったりすると「贈与」ではなく「売買」「労務対価」と判断されるリスクがあります。
日常の家事手伝いや週末の買い物程度では「扶養的贈与」とは認められず、生活費や学費を長期間にわたって全額負担していたといった客観的な量的・質的差異が必要です。
生前贈与は相続開始前10年以内、扶養的贈与は相続開始前いつからいつまで行っていたかが審査対象となり、期間が極端にずれていると評価を否定されることがあります。
最終的には遺産分割協議で全員の同意を取るか、調停・審判で裁判所が「特別受益として相続分調整を命じる」判断をしなければ、法的効力は得られません。
以上のように、単に贈与や立替があったという事実だけでは足りず、「贈与意思・無償性・特別性・時間的近接性・手続的合意・裁判所認定」の各要件を満たすことではじめて特別受益として認められます。
3.特別受益の清算
他の相続人が特別受益を認めた場合、遺産分割における公平性を保つために、特別受益を受けた相続人の相続分から受益分を減額して分配を行います。
特別受益を精算する手順としては、「①受益分を相続財産に持ち戻し」、「②受益分を含めた全体の相続財産を算出」、「③各相続人の法定相続分を算出する」「④特別受益を受けた者の持分から受益分を差し引く」という流れになります。
具体例を用いてご説明致します。
(例)相続財産が3,000万円あり、法定相続人が妻と息子達(長男1人、次男1人)の合計3人で、長男が500万円の特別受益を受けている場合
①まず長男の特別受益を相続財産に持ち戻します。
3,000万円+500万円=3,500万円
②相続財産は3,500万円とみなされます。
これを妻と息子達(兄弟2人)で分割するので③各自の相続額は以下の通りです。
妻の相続分は、3,500万円÷1/2=1750万円
長男と次男の相続分は、3,500万円÷1/4=875万円
しかし、長男は500万円の特別受益を受けているので、④その取得できる額は、875万円-500万円=375万円となります。
総合すると、
妻:1,750万円
長男:375万円
次男:875万円
ということになります。
4.特別受益が持ち戻されない場合
ところで、ある一定の場合には、特別受益が認められても、それが持ち戻されない場合があります。
最後に、どういった場合に持ち戻しが否定されるのかをご説明いたします。
まず、他の相続人から特別受益の持ち戻しの請求がなされない場合には、持ち戻しを行う必要はありません。
特別受益の制度は相続人間の公平を図る制度であり、当事者が公平を求めないのであればこれを適用する必要がないからです。
その他、被相続人が遺言や生前時に「特別受益について持ち戻しを行わない」という意思表示があった場合には、持ち戻しが免除されます。
これは、相続財産がもともと被相続人の財産であり、その分配に当たっては被相続人の意思を尊重する必要があるとの考慮に基づくものです。
但し、他の相続人の遺留分を侵害していた場合にはその限りではありません。
この場合には、遺留分侵害額請求の対象となり得ますので注意が必要です。
なお、持戻し免除の意思表示を行う場合、公証役場にて、その旨を記載した遺言公正証書を作成して備えることをお勧めします。
関連.持ち戻し免除と遺留分侵害額請求との関係
前述した通り、被相続人が生前に特定の相続人へ贈与や扶養を行った場合、持ち戻し免除の例外もありますが、結果として他の相続人の遺留分を侵害する場合はその限りではありません。
遺留分侵害額請求権により、免除された特別受益分も遺留分計算の基礎に加算され、遺留分侵害額請求の対象となり得ます。
この場合、遺留分算定で考慮すべき「贈与」は、相続人への特別受益に限らず、相続開始前に被相続人が無償で他者へ行ったあらゆる生前贈与を指します。
改正相続法では、遺留分算定の基礎財産に次の贈与分を加算することが明文化されています。
相続人への贈与:相続開始前10年以内の生前贈与(婚姻もしくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る)
相続人以外への贈与:相続開始前1年以内の生前贈与
これらを相続財産総額に加算し、法定遺留分比率(配偶者+直系尊属…1/3、その他…1/2)を掛けて遺留分額を算出します。
なお、遺留分侵害額請求を行う場合は、請求の時効がありますので時効期間内に請求をする必要があります。
関連リンク:●遺言書で自分以外の相続人が全財産を相続。これって仕方がないの?遺留分の計算方法と請求について
4.特別受益以外の他の制度との関係性
4-1.寄与分との違い・併用計算
特別受益は「相続開始前の利益享受」による調整、一方で寄与分は「相続開始前の貢献」に対する清算です。
両制度を併用するときは、まず遺産総額に特別受益を加算してみなし相続財産を算出し、みなし相続財産から寄与分を控除して算定基礎財産を算出し、算定基礎財産から法定相続分に応じた金額を算出し、特別受益がある特別受益がある場合には控除し、寄与分がある場合には加算して具体的相続分を算出します。
算定の手順例
- 1.遺産総額+特別受益=みなし相続財産
- 2.みなし相続財産-寄与分=算定基礎財産
- 3.(算定基礎財産×法定相続分)-特別受益+寄与分=具体的相続分
こうした順序で双方の制度を組み合わせ、二重控除や不公平を防ぎます。
4-2.債権者保護・債務控除との調整
被相続人の債務があるとき、相続人はまず債務の支払い義務を負います。
相続財産から債務を控除したうえで残余を基礎財産とし、特別受益の加算を行います。
例:
相続財産が5000万円、債務が2000万円、特別受益が500万円の場合
相続財産5,000万円-債務2,000万円=3,000万円(基礎財産)
特別受益500万円加算→3,500万円を法定相続分に応じて分割
このようにして、債権者保護と相続人間の公平を同時に図る仕組みとなります。
5.まとめ
以上の通り、特別受益は遺産分割に大きく関係してきます。
仮に、相続手続きの途中で特別受益に気づいた場合には、立証するには様々な資料収集を行わなければなりません。
特別受益が立証されると、遺産分割を初めからやり直したり、修正する必要などが出てくることから、多くの時間を費やさなければならない事態に陥ってしまいます。
話し合いが長期化しない為にも、専門家を活用する方法をお勧めします。
早めに専門家に相談をすることで、スムーズに相続手続きを進めることが可能になります。