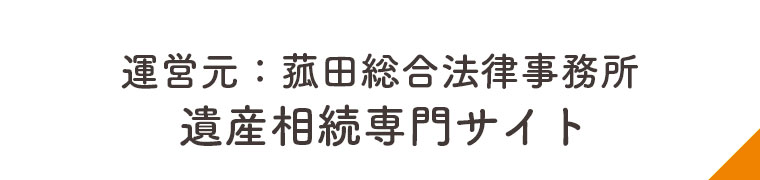遺言書で自分以外の相続人が全財産を相続。これって仕方がないの?
- HOME
- お悩み別コラム
- 相続で揉めている・預貯金の使い込み・生前贈与
- 遺言書で自分以外の相続人が全財産を相続。これって仕方がないの?
動画でわかりやすく解説!
「相続が発生したが、被相続人が自分以外の相続人に全財産を譲るという遺言書を遺していたため、相続財産が一切もらえない…」
このような場合、あなたはどうしますか?相続人の1人であるにも関わらず、被相続人の遺言書に全財産を特定の人物に譲ると記載されてあったら、この遺言書通りの相続が行われてしまうのでしょうか?
実は民法では、相続人に遺産の一定割合の取得を保証する「遺留分」という制度が定められています。
つまり上記のような場合であっても、遺言書で指定された相続人以外にも最低限の相続が保障されているのです。
今回は、この「遺留分」という言葉の意味と、遺留分を請求することができる「遺留分侵害額請求」という方法についてご説明します。
1. 遺留分ってなに?
遺留分とは、法定相続人が最低限取得できる相続の一定割合のことをいいます。
本来、人は誰しも自分の財産を自由に処分することができます。
第三者に財産を贈与したり、外部の団体に寄付したりとその処分方法は自由です。
被相続人が自分の財産について、どのように処分したいか、誰にどのように分配するかをきちんと遺言として遺しておけば、被相続人の遺産はその遺言に従って処理されます。
被相続人の遺言が残されていない場合、残された遺産は法律で定められている「法定相続分」という割合に従って相続人に分配されます。
一方、被相続人が遺言を遺している場合は遺言内容が優先されるため、遺言が特定の相続人にのみ財産を残すといった内容であったとしてもその通りに相続が行われる可能性が高いのです。
しかし、それでは遺言で指定された人以外の相続人が遺産を相続することができず、生活に支障をきたす可能性もあります。
本来相続には、相続人の生活保障及び遺産形成に貢献した相続人の潜在的持ち分を清算するという機能があります。
つまり、相続人には法律上定められた最低限の割合の利益を保護される権利があり、その権利が侵害された場合、相続人にはそれを請求できる権利があるのです。
この、相続人が相続財産の一定割合を法律上必ず確保できる権利、又は地位のことを「遺留分権」といいます。
2. 遺留分の権利者とその計算方法
法定相続人に最低限の相続分として保障される遺留分ですが、全ての法定相続人に保障されているわけではありません。
遺留分が保障されるのは、法定相続人のうち被相続人の配偶者、被相続人の子、および直系尊属に限定されています。
兄弟姉妹には遺留分は保障されていません。
また、被相続人の子の代襲相続人は、被代襲者と同じ遺留分を持ちます。
保障される遺留分の割合は、相続人にどの立場の人がどれくらいいるかという状況によって異なります。
相続人が被相続人の直系尊属のみの場合、遺留分の割合は法定相続分の3分の1になります。
その他の場合、つまり相続人に配偶者等の直系尊属以外の相続人もいる場合は、遺留分の割合は法定相続分の2分の1になります。
それでは、具体的に自分の遺留分の割合を計算するには、どうしたらいいのでしょうか。
遺留分の割合を計算するには、まず遺留分算定の基礎となる財産を計算する必要があります。
遺留分算定の基礎となる財産は、以下の方法で計算します。
=被相続人が相続開始時に有していた財産+生前贈与した財産※―債務
この遺留分算定の基礎となる財産の額を算定したら、それに遺留分の割合を乗じた額が遺留分となります。
なお、遺留分権利者が生前に被相続人から贈与を受けていた場合は、特別受益として遺留分から控除されます。
※相続人に対して行われた贈与であれば、相続開始から遡って10年、相続人以外の方に対して行われた贈与であれば遡って1年以内のもののみが対象となります。
3. 遺留分侵害額請求の方法について
遺留分権利者が、相続人や受遺者に対して侵害された遺留分(遺言や贈与によって最低限保障される相続財産の取り分)を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求をする場合、通常は遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して「内容証明郵便」という方法を使って 遺留分侵害額請求権の行使の通知書を送ります。
遺留分侵害額請求には時効があり、①被相続人の死亡の事実、②自分が相続人であること、③遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知ってから1年以内に遺留分侵害額請求をしなければなりません。
期間内に遺留分侵害額請求権の行使の通知を行い、遺留分侵害額請求権の消滅時効の完成を防いだことを証明するために、通知内容と日付の控えが残る内容証明郵便を用いるのです。
また、被相続人が死亡したことを知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求の権利はなくなってしまいます。
このことを除斥期間と言います。
遺留分権利者は、通常、遺留分侵害額通知を行った後に交渉を行い、遺留分の返還について受遺者の合意を得ることができたら、遺留分の返還を受けることができます。
しかし、交渉がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立て、調停での話し合いで協議を行うことになります。
調停でも話がつかなければ、裁判をする必要があります。
遺留分侵害請求は、裁判をする前に調停をしなければなりません(これを調停前置主義といいます。)。
4. 遺留分を請求する前に相続財産の処分を防ぐには?
遺留分侵害額請求を行う前に、相続人が相続財産を勝手に処分してしまうと、請求が認められても現実に回収できないおそれがあります。
こうしたリスクを避けるために、実務においては以下のような財産の処分を防ぐ手続きを遺留分侵害額請求と併用することもあります。
1.仮差押え
何をする?
裁判所から、財産の処分を禁止する命令を出してもらう手続です。
- • 目的:将来の本訴(不当利得返還請求や損害賠償請求)の金銭債権を確実に回収できるよう、相手の具体的な財産を「差し押さえて」おく
- • 対象財産:預貯金口座、公示前の不動産、株式など金銭換価が容易な財産
- • 効果:裁判所が仮差押命令を出すと、相手は差し押さえた財産を処分(売却・譲渡・引き出し)できなくなります。
メリット
• 相続人が財産を隠匿・処分する前に遺留分の支払い原資を確保できる
2.仮処分
何をする?
仮差押えよりも広く「ある行為」をさせない・させ続けるよう命じてもらいます。
- • 目的:本訴で請求する「行為の禁止」や「義務の履行」を事前に確保するため、特定の行為をやめさせる(またはさせる)
- • 効果:
禁止型 相続財産の売却・譲渡など「行為」を禁止する
義務付け型 口座残高証明の提出や帳簿の閲覧を「義務」として命じる
メリット
• 財産の形を問わず、行為そのものをストップできる
3. 仮差押えと仮処分はどう使い分ける?
仮差押えと仮処分はどちらも「保全手続」ですが、目的と効果に次のような違いがあります。
| 仮差押え | 仮処分 | |
|---|---|---|
| 対象 | 具体的な財産(預貯金、不動産等) | 行為自体(売却・譲渡・引出し) |
| 効果 | 財産が動かせなくなる | 指定した行為ができなくなる |
| 用途 | 回収可能額を確保 | 今後の不正処分を予防 |
| 担保 | 原則として保証金・担保提供が必要 | 原則として保証金・担保提供が必要 |
上記をまとめると、
- • 「請求できる金額を確保したい」→ 仮差押え
- • 「財産が外部へ流出するのを止めたい」→ 仮処分
両者を併用することで、請求権の実効性確保(差押え)と不当処分の予防(処分禁止)を同時に抑制できます。
具体的な事情に応じて使い分け、またはセットで申立てることが実務のポイントです。
4. まとめ
今回は、遺留分という言葉の意味と、遺留分侵害額請求の方法についてご説明しました。
相続において、被相続人が、特定の相続人にのみ財産を与えるという遺言を残すことは珍しくありません。
相続人の方は、被相続人の遺言の内容を見て、明らかにご自身の相続分が少ない、あるいは全くないという場合には、遺留分侵害額請求について検討してみましょう。
ただ、遺留分侵害額請求を行うには、遺留分の金額を正確に計算し、時効までに遺留分侵害額請求権の行使の通知書を作成して受遺者に送付する必要があります。
また、交渉が難航して話し合いで解決しない場合は、法的手続きに移行し調停で協議を行う必要があります。
遺留分侵害額請求の手続きをスムーズに行うためには、相続の専門家や弁護士に相談したほうが良いでしょう。