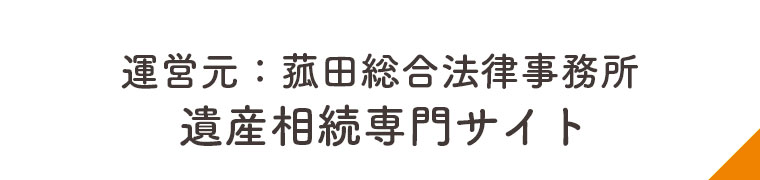遺産分割協議と協議書の作成
- HOME
- お悩み別コラム
- 相続で揉めている・預貯金の使い込み・生前贈与
- 遺産分割協議と協議書の作成
動画でわかりやすく解説!
「遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成する」ということを聞いたことがあるけど、遺産分割協議書って必ず作成しなければならないの?
また、どのように作成したらいいの?
このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
今回は、遺産分割協議書について、その作成の前にやっておくべきことと、作成時の注意点についてご説明します。
1. 遺産分割協議書って?
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割協議を行った結果をまとめた書面のことです。
遺産の分割方法及び金額について、相続人全員が合意したことを証明する意味があります。
そもそも、遺産分割手続きとは相続人全員の合意によって行われる手続きであり、合意を形成する手段は相続人らの自由とされています。
一般的には、相続人全員が一同に集まり協議する場合が多いですが、相続人の人数が多い場合や、遠隔に住んでいる相続人がいるため集まることが難しい場合、又一度も会ったことがなく相続人同士の面識が全くない場合等、直接協議を行うのが困難な場合は電話や書面を通して協議を進めることも可能です。
そして、相続人全員の間で合意が成立したら、合意内容に不満を持つ相続人が協議を蒸し返したり、協議に参加しなかった等の主張をしたりしないように、協議内容を証明するための遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないというものではありません。
しかし、不動産の相続登記や相続税申告、また預貯金の払い戻し手続き等の相続手続きの際に、遺産分割協議書が必要になることがあります。
相続手続きを円滑に進めるため、また相続人間でトラブルになるリスクを避けるため、遺産分割協議を行った後は出来る限り遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。
2. 遺産分割協議書の作成前にやること
遺産分割協議書に協議内容を正確に記載するため、遺産分割協議書作成の前に以下の項目を必ず確認しておきましょう。
(1) 相続人を確定させ、その意思を確認する
遺産分割協議書は相続人全員の合意がなければ無効となってしまうため、最初に相続人が何人いるのかを確認しなければなりません。
そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、全ての相続人を特定する必要があります。
今まで相続人は配偶者と子供だけだと思っていたが、実は被相続人が過去に結婚していて子供がいた場合、前妻との子供も相続人に含まれます。
このように、戸籍を確認して初めて相続人が他にもいることが判明するケースもあるため、必ず被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認しましょう。
(2) 相続財産の内容を確認する
相続人が確定したら、次は相続財産の確認が必要です。
遺産分割協議は相続人全員の合意があれば自由な内容で行うことが可能なため、不動産についてのみ協議を行い預貯金については法定相続分通りに分割するといった協議を行うことも可能です。
しかし、後に現在判明していない相続財産が発見され、これをめぐって相続人間でトラブルになることがないよう、遺産分割協議を行う段階で全ての相続財産を特定しておくことが望ましいです。
具体的には、相続財産の内容によって以下の方法で調査することができます。
・ 不動産
役所で被相続人名義の固定資産評価証明書を取得すると、被相続人の所有している不動産及びその固定資産評価額を確認できます。
不動産の正確な情報を把握するため、法務局で不動産の登記簿謄本を取得しておきましょう。
登記簿謄本は、不動産会社の無料査定を行う場合や、後の相続税申告の際にも必要となります。
・ 預貯金
預貯金の残高は、金融機関で発行される残高証明書で確認することができます。
残高証明書には預貯金のみでなく借入金の残高も載っているため、被相続人の借入金も確認することができます。
また、被相続人の口座の支店や口座番号が不明な場合は、金融機関で照会を行うことが可能です。
3. 遺産分割協議書作成の注意点
遺産分割協議書を作成する際は、以下の点に注意して作成しましょう。
(2) 氏名・住所は、住民票や印鑑登録証明書の通りに記載する。
(3) 相続財産の内容を正確に記載する。
不動産の場合は、登記簿謄本や権利証に照らして所在と地番・家屋番号を正確に記載する。
預貯金や有価証券などは、通帳や証券に照らして正確に記載する。
(4) 各相続人は直筆で署名し、実印で捺印の上印鑑登録証明書を添付する。
(5) 相続人の人数と同じ通数を作成し、各相続人が1通ずつ手元に保管する。
(6) 協議書が複数枚にわたる場合は、各用紙の間に全相続人の契印をする。
(7) 現在判明されていない相続財産が今後発見された場合、誰にどのように分配するか、若しくは再度相続人全員で協議を行うのかについても記載する。
遺産分割協議書への署名の際に、万が一訂正が必要となった場合は、訂正箇所に二重線を引き上から訂正印を押し、空いている箇所に正しい内容を記載します。
また、押印の際に実印の淵が欠けてしまった場合や内側の文字部分が欠けてしまった場合は、隣に再度押印しましょう。
また、遺産分割後の相続手続きの際に、金融機関や証券会社等では遺産分割協議書だけでなく各社専用の様式の書類に署名捺印する必要がある場合があります。
あらかじめ金融機関や証券会社等に確認を行い準備しておくと、遺産分割協議書の作成時に同時に準備することが可能です。
4.二次相続・代襲相続を見据えた遺産分割の重要性とは?
一次相続(両親のうち一方が死亡)で遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成する際、残された配偶者の生活確保だけに注目すると、子にとって将来の二次相続(もう一方の両親が死亡した段階)で多額の相続税負担が生じることがあります。
たとえば自宅と預金をすべて配偶者が取得すると一次相続では〈配偶者の税額軽減〉で税金ゼロでも、二次相続では、小規模宅地等の特例が使えず、評価額そのままで課税対象となる可能性があります。
また代襲相続(子が相続開始前に死亡し孫が相続人になる)を想定せず作成すると、孫の持分を調整する再協議が必要になる場合があります。
協議書に「将来代襲相続が発生した場合は本協議書に従い持分を承継する」「配偶者居住権を設定し、負担付所有権は長男が取得する」といった条項を盛り込むことで、二次相続・代襲相続双方のリスクを低減できます。
加えて、配偶者が取得する資産を流動性の高い預金中心にする、子が将来利用しない収益不動産を一次相続で子へ移転しておく–など“二段階相続シミュレーション”を行い、協議書に反映させることが賢明です。
この辺りについては、遺産分割協議書を作成する段階で相続に強い弁護士・税理士に相談の上で、一次相続と二次相続を通算した遺産分割方法を検討し、できるだけ税負担を最小化できるようにしていくことをお勧めします。
5.作成した遺産分割協議書が無効になってしまうケースとは?
①遺産分割協議が無効となる場合
1)相続人欠缺:相続人となる人のうち、一部を見落としていて遺産分割協議書への記載が漏れていた場合。
後日、新しく相続人が判明すると、遺産分割協議そのものが無効となり、すでに作成した協議書も法的効力が無くなります。
2)意思能力欠如:相続人のうち意思能力がない人がおり、その状態にもかかわらず本人が署名押印をした場合。
判断能力がない相続人がいる場合、本人の代理として後見人もしくは特別代理人を介さずに行った遺産分割協議は無効となります。
3)特別代理人選任を怠った場合:親権者と未成年の子の両者が相続人となる場合は、双方が利益相反の関係となり、親が子の法定代理人として遺産分割を行うことができないため、特別代理人の選任が必要となります。
これをせずに、親権者が未成年子の代理として署名した場合は遺産分割協議は無効となります。
4)協議内容に公序良俗に反する内容が含まれている場合:遺産分割協議書の中に公序良俗に反する内容の条項が含まれている場合は、その条項については遺産分割協議が無効となります。
なお、無効となる条項が遺産分割協議全体に大きく影響を及ぼす場合は遺産分割協議自体が無効となる可能性があります。
②遺産分割協議が取消となる場合
1)脅迫・詐欺・錯誤があった場合:強迫的な説得で遺産分割協議書に署名をさせた、財産の存在を隠したまま協議を進められた、遺産分割の内容について重大な勘違いをしたまま署名をしたというような場合、民法第95条(錯誤)、96条(詐欺又は強迫)の要件を満たしていれば協議の取り消しが認められる場合があります。
5-1.遺産分割協議書の形式的な不備があった場合はどうなる?
作成した遺産分割協議書の中に誤りを見つけた場合ですが、①単純な記載不備(明らかな誤字脱字など)と ②遺産分割協議自体に影響する記載不備(相続財産の記載漏れなど)のどちらに該当するかで対応方法が異なります。
①のような軽易な記載ミスであれば、すでに全員が合意している前提を崩さずに、訂正印での訂正(もしくは捨印での訂正)で足りることが多いです。
ただし、②のように相続財産に漏れがあったり、財産の金額が大幅に変動するような記載ミスがあったりするような場合は、その訂正を行うことで実質的に遺産分割内容が変わってしまうため、正しい内容での遺産分割協議書を再度作成し、相続人全員からの署名押印を再度取り付けることが必要となります。
なお、訂正印や捨印での訂正については、登記手続や金融機関での手続きを行う上では場合によっては認められないこともありますので、その場合は再度遺産分割協議書の作成が必要となります。
一度作成した後での修正手続きができるだけ発生しないよう、遺産分割協議書を作成する際は、以下のような点に十分留意の上で、内容に間違いがないかを念入りに確認の上で署名押印を行うようにされてください。
- ・誤字・脱字がないか
- ・被相続人の記載が誤っていないか
- ・相続人の記載が誤っていないか
- ・相続財産の記載が誤っていないか
- ・押印している実印が誤っていないか
6.遺産分割協議書を公正証書にしておくメリット
遺産分割協議書の公正証書化は必須ではありませんが、以下のようなケースでは公正証書化しておいた方が後々のリスク回避のためには有効な場合があります。
- ・相続人が高齢のため本人の意思での署名かどうかに後で疑義が生じそう
- ・遺産総額が非常に高額で協議書の偽造等が容易にできないようにしておきたい
- ・協議で定めた代償金の支払いについてきちんと実行されるか不安がある
公正証書にすると、公証役場にて公証人立会いの下で遺産分割協議書を作成するため署名押印の真偽で争う余地がほとんどないほか、遺産分割協議書の原本は公証役場にて保管されるため偽造紛失の恐れもありません。
さらに、公正証書自体には執行力は備えないものの、内容が金銭給付条項を含む場合は「執行認諾文言」を付けることで強制執行の要件を満たすこともできます。
そのため、例えば、代償金支払の条項を入れる際に、「本証書に記載された支払いを行わなかった場合は、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」というような文言を付けておくことで、代償金の支払いが滞った場合は強制執行の手続に移行できます。
公正証書でない遺産分割協議書の場合は、まずは裁判所へ訴訟提起の上で、強制執行を行うための債務名義の取得からする必要があり、お金を支払ってもらえない状況であってもすぐに強制執行をすることはできません。
支払いをしてもらうために費用と手間をかけて裁判をしなければならないというのは本人にとっても負担が大きいため、少しでも不安があるような場合は公正証書にしておくとリスク回避が可能です。
なお、公正証書作成の費用については、「遺産総額×およそ0.1%」が目安です。
たとえば遺産が1億円なら手数料は十万円と少しです。
大きなお金が動く相続手続において、安心を買うコストとしては、決して高すぎることはないかと思いますので、ご自身の状況に応じて必要であれば公正証書化を検討してみられてください。
7.本コラムのまとめ
遺産分割手続きをスムーズに行うために、遺産分割協議書を正確に作成することは非常に大切です。
遺産分割協議書の作成を誤ってしまうと、協議書が無効になってしまうこともあるため、作成方法がわからない場合や作成に不安な点がある場合は早めに弁護士に相談しましょう。
当事務所では、相続案件に特化した弁護士を中心に、遺産分割協議書の作成を含めて相続に関するご相談をワンストップでご対応しております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。