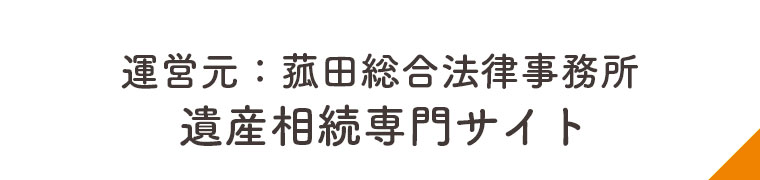相続人が預貯金を使い込んだらどうすればいい?預貯金の開示手続きと使い込みへの対応
- HOME
- お悩み別コラム
- 相続で揉めている・預貯金の使い込み・生前贈与
- 相続人が預貯金を使い込んだらどうすればいい?預貯金の開示手続きと使い込みへの対応
動画でわかりやすく解説!
他の相続人が被相続人(亡くなった方)の預貯金を使い込んでいた場合、そのまま遺産分割の話し合いを進めてしまうと、相続人同士の間に不公平が生じてしまいます。
それでは、公平に遺産分割を行うには、どのように手続きを行えば良いのでしょうか?
相続でしばしば問題となる「預貯金の使い込み」は、財産調査や返還請求など多くの手続きが絡み、家族間の紛争も深刻化しがちです。
本コラムでは、その具体的な解決策や法的なポイントを弁護士が解説します。
1.預貯金の使い込みについて
一般的に、被相続人が亡くなるまでの間、自身で金銭管理を行っていれば預貯金の使い込みというトラブルは発生しません。
亡くなる前の段階で親族等に金銭管理を依頼している場合に発生するケースが多くみられます。
遺産分割の話し合いの際に、被相続人の通帳を確認してみると、普段からあまりお金を使わない生活をしていたにも関わらず、何度も纏まった出金がある場合や、被相続人が金銭管理能力を失った時期以降に必要以上の出金が確認される場合があります。
これらに該当するような不審な出金が確認されると、誰が出金して、何のために使用したのか?と、遺産分割協議において問題になるケースがあります。
他の親族が使い込みをしたのであれば相続人は返還を求めることが可能です。
どの様な過程を経て、どの様な権利に基づいて返還を求めるのか、解決までの流れをご説明いたします。
2.調査から解決までの手順
預貯金の使い込みを調査する場合、様々な資料収集が必要になります。
大きな流れとして、①被相続人の取引履歴を取得し、②取引履歴等の検証の手続きを行います。
(1)被相続人の取引履歴を取得する
相続人は相続権に基づいて、被相続人が預金口座を保有していた各金融機関に対し取引履歴などの口座情報について開示を求めることが出来ます。
各金融機関により資料の取得のための必要書類は異なりますが、一般的には、相続人である事を示す戸籍、亡くなられた方の死亡が確認できる戸籍、印鑑証明書、身分証明書等の書類の準備が必要となります。
必要書類については、金融機関によって異なるため、事前に問い合わせを行うことをお勧めします。
被相続人に関する情報については、相続人であれば問題なく開示されます。
しかしながら、送金先の口座情報を開示するとなると、第三者の個人情報となるため、たとえ相続人からの依頼であっても金融機関は情報開示に応じません。
送金先を確認したい場合には、弁護士などの専門家を通した開示請求を行うことにより、金融機関から回答を得られる可能性があります。
(2)取引履歴等の検証
取引履歴等の資料取得が完了したら、次に、使途不明金や多額の送金履歴など、不審な取引をピックアップしていきます。
被相続人の過去の生活状況等も含め、不自然な点が無いか検証を行います。
法的に請求が可能となる取引内容の有無については、専門的な知識が必要となるため、専門家に相談をしながら検証を行うことをお勧めします。
検証結果が出たら相続人同士で話し合いを行いましょう。
(3)返還請求
返還請求について相手との協議で解決に至らない場合には、裁判所を利用して解決を図ることになります。
具体的には、遺産分割調停の申立、不当利得返還請求訴訟、又は、損害賠償請求訴訟の提起といった手続きが考えられます。
相続人同士だけで、話し合いによる解決を図ろうとして協議や調停を行うと、感情の問題が前面に出てしまうため、紛争が長期化してしまうケースが多々あります。
感情論に左右されず建設的な協議を可能にするためには、代理人を立てて、対応されることをお勧めします。
3.返還請求を求められた場合
被相続人の金銭を管理していた場合、遺産分割協議の際に、他の相続人から使い込みや特別受益の請求を受けることもあります。
返還請求を受けている出金の使途が適切なものであるなら、他の相続人から指摘を受けた際に適切な出金であったことを主張する必要があります。
主張を裏付けるために、客観的な証拠(領収書・贈与契約書など)の準備も必要となります。
使い込みを否定したいときはどうしたらよい?
使い込みを疑われたとしても、疑われた側としては「実はこれは正当な報酬として本人から生前贈与を受けていた」「本人が口頭で『好きに使っていいよ』と言ってくれた」などの事情があり、使い込みではないと反論したいケースもあるでしょう。
ただ、生前贈与を含めて口頭だけの約束だと立証が難しいため、後から書面や客観的な根拠を示せなければ裁判では不利になりやすいです。
相続開始前に正当な贈与があった場合は、贈与契約書をきちんと作成する、本人の意思を記した書面を作っておくなど、客観的な根拠として使える書面を残しておくことが望ましいです。
既に相続が発生してしまっている、かつ客観的な書面が存在しない場合は、メモ書きや家族の証言など現時点での可能な限りの証拠を揃えられるようにしましょう。
関連:民法上の「不当利得」とは何か?
預貯金の使い込みに対して返還を求めるときに使われる法的な概念が不当利得です。
民法703条では「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定しています。
「法律上の原因がない」とは、例えば遺言や贈与契約といった正当な手続きがないことを指しており、他人の財産で利益を得ているのだから、本来の所有者へ返還義務があるという考え方になります。
つまり、亡くなった方の通帳から無断でお金を引き出し、自分のために使った場合は、法律的に見て「正当な根拠のない利得」とみなされやすいのです。
特に相続においては、被相続人の生前、特定の親族が預金を管理していたにもかかわらず、その資金を自分の目的で流用していた場合、他の相続人は「それは相続財産を勝手に取り込んだ行為だ」とみなして返還を求めることになります。
4.預貯金の使い込みには刑事責任は問えるのか?
4-1.親族間の使い込みは刑法上どう扱われる?
預貯金を「勝手に」引き出して使っていた場合、刑事上の罪に問われる可能性もあります。
例えば、私的流用した行為が横領罪(刑法252条)や背任罪(刑法247条)に該当し得ることがあるからです。
横領罪:他人から預かった物を自己の物のように扱う行為。
背任罪:財産管理の委託を受けている者が、任務に背き他人に損害を与えた場合。(親族の間で後見業務を行っていたようなケースで、後見人が不当に財産を抜いていたような例)
とはいえ、家族間で告訴するかどうかは当事者の判断に委ねられ、告訴すれば必ずしも立件されるとは限りません。
むしろ、刑事事件として進めると家族関係が一層悪化する恐れがあるため、実際には民事的な返還請求で決着を図る例が多いです。
4-2.刑事告訴と民事請求の違い
刑事告訴は「犯罪として処罰してほしい」という趣旨で進める手段なので、相続人としては「返還させる」「被害弁償をさせる」ことが主目的なら、民事の返還請求や遺産分割調停を優先した方が現実的です。
一方、「まったく悪びれない態度で巨額を使い込みした」「話し合いに応じず開き直っている」など深刻な状況なら、刑事告訴を検討するケースもあるでしょうが、実務上は刑事事件化するケースはそこまで多くはありません。
5.遺産分割協議において使い込みをどう調整するか?(特別受益・寄与分との調整)
5-1.使い込んだ分を特別受益として扱う場合
預貯金の使い込みが起こった場合でも、不当利得返還請求まで行かず、遺産分割協議の中で「実質的に生前贈与されたようなもの」として取り扱う方法をとるケースもあり得ます。
たとえば、介護を担っていた子が生活費や介護費用以外に多額を引き出していたのは事実だが、他の相続人もそのことを理解している場合は、「それを特別受益として持ち戻し計算し、遺産分割で差し引く」という形です。
この場合は、民事訴訟をせずに協議ベースで解決が図られる可能性が高いので早期解決も見込めます。
5-2.使い込んだ分と寄与分との同時主張
逆に「親のために相当な介護・看護をし、費用も負担してきた。その対価として日々の出金をしていた」という立場を取るなら、寄与分として自らの貢献を評価してもらう道があります。
もっとも、法律上の寄与分は「特別の寄与」が要求されるため、当人の寄与が本人の財産維持・財産増加に貢献しているという客観的な判断ができなければ寄与分は認められません。
寄与分と預貯金の使い込みの両者が混在した場合、たとえば「使い込みの一部は正当な寄与分として資金を受け取る形になっていたが、残りは不当利得だ」というように一定のラインでの線引きがされるようなケースもあります。
特別受益、寄与分いずれも法的な観点で考慮すべき点が多いため弁護士に依頼の上で進めるのが望ましいでしょう。
6.裁判手続きをどう使うか—遺産分割調停と不当利得返還訴訟の違い
預貯金の使い込みの問題を解決するためには「不当利得をどう考慮して遺産分割を行うか」という点にかかってくるのですが、実務上の裁判所での手続きについては家庭裁判所での手続をするか、地方裁判所での手続きをするかの2パターンの手段があります。
6-1.遺産分割調停で同時に解決を図る
家庭裁判所の遺産分割調停では、基本的に「遺産をどう分けるか」に重点が置かれますが、預貯金の使い込みの返還をどう扱うかという点も一緒に話し合いをすることが可能です。
「実際には〇〇円を引き出していた。それを相続財産に加算して分配計算すべきだ」と主張し、調停委員の仲介を得ながら協議を進めます。
メリット:相続手続の中で一緒に解決が図れるので効率的に遺産分割が進められる。
デメリット:純粋に金銭返還請求が争点となっている、あるいは「相続財産に含まれるかどうか以前に、別の法的争点(詐害行為や横領など)を巡って対立がある場合は調停での話し合いだけでは解決ができない(別途民事での訴訟が必要)
6-2.不当利得返還請求訴訟を別途提訴する
「遺産分割とは別として使い込んだ分を返してほしい」というような場合は、遺産分割調停とは別に不当利得返還請求を民事訴訟として提起することとなります。
なお、相続人以外が使い込みを行った場合(内縁関係のパートナーなど)は相続人ではないので遺産分割協議の中での解決はできないため、訴訟にて返還請求を行う必要があります。
メリット:裁判所の判決によって返還額が確定すれば強制執行が可能。
デメリット:判決が出るまで時間と費用がかかる。
客観的な証拠が不十分である場合は敗訴するリスクがある。
状況に応じては、不当利得返還請求と同時に、損害賠償請求や詐欺・横領に基づく刑事責任を追及する手段も検討し得るため、こちらも弁護士に相談の上で対応を依頼するのが望ましいでしょう。
Q&A:預貯金の使い込みに関するよくある質問
Q.「使い込み」かどうかを判断する基準は何ですか?
最終的には、被相続人の同意や意向があったかどうかが焦点となります。
単に「家族だから自由にお金を使ってもよい」といった曖昧な話ではなく、明示的な贈与契約や介護費用としての支出だったのかなど、法的根拠が必要です。
単なる口頭の主張だけでなく、領収書・銀行の振込明細・メールやメモなど具体的な証拠がないと、客観的に使い込みと認定されやすいでしょう。
Q.被相続人が軽い認知症だった場合、出金はすべて不当利得に当たりますか?
一概にそうとは限りません。
ごく日常的な出金や医療・介護費用の支払いは正当な支出として認められる場合があります。
問題となるのは、それ以上に明らかに不自然な多額出金や、被相続人の意思能力を超えた「大規模な財産流用」などです。
どの時点から判断能力が欠如していたかなど、医療記録や周囲の証言が判断材料となります。
Q.他の相続人に「使い込み」を疑われ、身に覚えがない場合の対処法は?
使い込みの事実がないことを主張するためには、まずは領収書や振込明細、被相続人とのやり取りメモなど、客観的な証拠を提示することが重要です。
たとえば本人の介護に伴う支出や、被相続人が「自由に使っていい」と言った場面の記録があれば、単なる横領ではない可能性を示せます。
主張を裏付ける資料をきちんと揃え、相手が納得しない場合は弁護士とともに協議や調停・訴訟で正当性を争うことになります。
7.本コラムのまとめ—「使い込み」は放置せず早めの調査と行動を
預貯金の使い込みが疑われる場合、使い込みを立証し、解決をおこなうまでには、多くの資料収集や検証などが必要になります。
どの程度の資料があれば良いのか、それをもとにどういった請求方法があるのか、的確に判断するには実務経験の豊富な専門家に相談する必要があるでしょう。
また、被相続人となる方の財産を管理されている方は、トラブルを未然に避けるためにも、領収書などはきちんと保管し、正当な出金であることを証明できるように備えておくことが必要です。
もし自分が使い込みを疑われてしまった側であっても、適正な支出であったことを裏付ける証拠があれば不当利得ではないときちんと主張することが可能です。
当事務所では、複数の士業が在籍する強みを活かし、相続に関わるあらゆる問題をワンストップでサポートします。
預貯金の使い込みを含む相続紛争や、関連する相続手続についてのご相談は、ぜひ相続LOUNGEの初回無料相談をご利用ください。