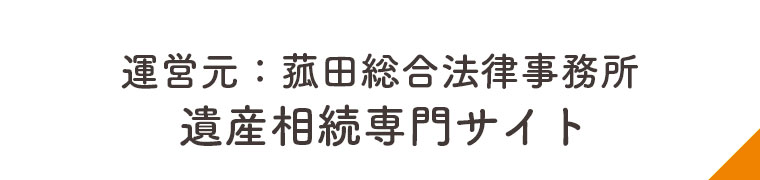遺留分と特別受益・侵害額請求とは?
- HOME
- お悩み別コラム
- 相続で揉めている・預貯金の使い込み・生前贈与
- 遺留分と特別受益・侵害額請求とは?
動画でわかりやすく解説!
遺産相続において、被相続人が生前に特定の相続人へ大きな援助をしていた、遺言書で特定の人を優遇していた場合、遺留分の問題が出てきます。
今回のコラムでは、遺留分を算定するうえで特別受益がどのような影響を与えるのかを中心に、弁護士が解説をしています。
このコラムを読んでいただくことで、遺留分を考える際にどのような点が争点となり得るのか、実際に遺留分を請求する際の注意点などをイメージしやすくなるはずですので、弁護士へ相談する際の参考になさってください。
1.遺留分とは?
そもそも遺留分とは、一体何のことでしょうか?
遺留分というのは、法律上、相続人に保障されている一定の割合の相続財産のことを言います。
この場合の相続人というのは、直系尊属、直系卑属、配偶者となります。
兄弟や姉妹は含まれません。
・直系尊属
直系というのは、血のつながりを有している縦のラインの親族のことを指します。
尊属は、自分を中心とした場合、自分よりも前の世代の人のことを指しますので、具体的には祖父母や父母のことです。
・直系卑属
直系は、先程と同じく縦のラインの親族のことで、卑属とは、自分を中心とした場合、自分よりも後の世代の人のことを指します。
つまり、子や孫、ひ孫のことを表す言葉となります。
遺留分の割合としては、誰が相続人になるのかによって変わってきます。
① 直系尊属のみが相続人となる場合
→被相続人の財産の3分の1
② 直系卑属あるいは配偶者が相続人となる場合
→被相続人の財産の2分の1
ここでいう被相続人の財産とは、一般的な相続財産のことではなく、「遺留分算定の基礎となる財産」のことを指します。
「遺留分算定の基礎となる財産」の代表的な算定方法は以下のとおりになります。
- ① 被相続人が相続開始時において有していた積極財産
- ② 相続人に対して相続開始前10年間になされた贈与
- ③ 相続人以外に対して相続開始前1年間になされた贈与
- ④ 相続人が受けた特別受益
以上の項目を計算し、そこから被相続人が負っていた債務を控除します。
これらの計算によって算出された額が「遺留分算定の基礎となる財産」となります。
関連:遺留分算定の基礎財産についての補足
先ほどもお話したとおり、遺留分を計算する際の「財産」というのは、単に被相続人が死亡時点で保有していた資産だけを指すのではなく、①生前に行われた一定の贈与や、特別受益にあたる贈与・遺贈を加算、②さらに被相続人の債務を差し引いた総額であることがポイントとなります。
この「遺留分算定の基礎となる財産」をきちんと把握できないと、どの程度が遺留分を侵害しているか判断しづらいでしょう。
たとえば、死亡時点では1,000万円しか預金がないと思っていても、実は5年前に特定の相続人に2,000万円を生前贈与していた場合、その2,000万円を合算して3,000万円を財産の額として遺留分を算出するといった具合です。
一方で「10年以上前の生前贈与」「通常の扶養の範囲内」とみなされる支出は、必ずしも算定に加わらない場合もあるため、具体的な時期や金額を個別に評価する必要があります。
2.特別受益と遺留分の関係
遺留分を算定する際の基礎財産を把握する際に考慮すべき事項として、「特別受益」という言葉が出てきましたが、遺留分を考えるうえで特別受益は重要な要素の一つです。
2-1. 特別受益と実際の例
特別受益とは、被相続人が生前に特定の相続人に対して通常を超える援助や贈与を行った場合、それを「相続開始前に前渡しされた遺産」として扱う考え方です。
典型的には以下のようなものが挙げられます。
- •住宅資金や結婚資金の援助
- •不動産や高額な株式の生前贈与
- •結婚・養子縁組の際の多額の祝い金 など
これらが「他の相続人に比べて明らかに厚遇されている」とみなされた場合、遺産分割や遺留分の計算時に調整される可能性が高くなります。
2-2. 遺留分請求の実務における特別受益の取り扱いのポイント
・特別受益の時期
2019年7月の民法改正で、10年以上前の贈与は遺留分算定の対象外になると定められました。
これは「被相続人が亡くなる10年を超えて前に行われた贈与は、いわゆる“特別受益”として持ち戻す必要がない」という考え方が基本です。
ただし、これはあくまでも一般的ルールであり、全ての贈与が無条件で完全に除外されるわけではないため遺留分算定の際は注意が必要です。
なお、特別受益として考慮するとなった場合は、相続開始時(死亡時)の評価額で計算することとなります。
・特別受益に当たるか否かの判断基準と争点
特別受益の典型例として学費や結婚資金を紹介しましたが、これらのすべてが特別受益に該当するわけではありません。
特別受益に当たるかどうかという判断の際は、「一般的な扶養の範囲を超えるかどうか」「被相続人の財産規模や他の兄弟姉妹との比較」などの要素も考慮されます。
例えば、長男だけ私立大学の学費を全額負担してもらったという場合でも、それが社会通念上通常の範囲とみなされるか、特別に優遇されたといえるのかというのが実務上でも争点となり得ます。
また、「家賃の敷金を一時的に立て替えてもらった」「ちょっとした引っ越し代を援助してもらった」など、比較的“小口”あるいは“日常的”な金銭的サポートも特別受益となるのかというところも判断が分かれるところです。
一般的には、金額自体が小さい場合は通常の扶養の範囲内とみなされやすいですが、累計すると高額になる例もあり、その場合は他の相続人との比較で不公平感が生じるかどうかがポイントとなります。
この辺りは事例によって判断がまちまちですので、遺留分算定の際は個別事情を考慮の上で取り扱うこととなります。
3.特別受益があると特定の相続人を優遇することはできないのか?
3-1.特別受益を考慮しないでほしいという意思表示はできる
生前贈与の仕方と内容によっては特別受益にあたるため、相続財産に持ち戻されてしまうのですが、とはいえ中には一定の相続人を優遇してあげたい(生前贈与は考慮せずに相続財産を算定してほしい)と思う方もいらっしゃると思います。
その場合は、被相続人が生前の特別受益については考慮しないでよいという意思表示をすることもできます。(これを、特別受益の持ち戻し免除といいます。)
この意思表示については、口頭などでも構わないとされていますが、遺言書などの書面に明記しておくことが確実な方法です。
3-2.持ち戻し免除の意思表示ですべての遺留分請求を防ぐことはできない
「被相続人が特別受益を考慮しない」と明言していれば、特別受益を受けた相続人は安心できそうに思えます。
しかし、特別受益の持ち戻し免除の結果、遺留分を侵害された相続人が出てきてしまった場合、被相続人の意思があるからといって最低限の相続分をもらえないとなってしまうと、相続人の権利保障を目的とした遺留分の制度の趣旨が満たされなくなってしまいます。
そこで、このような場合には遺留分が侵害されている範囲で持ち戻しの免除は効力を失うものとされています。
これにより、特定の相続人の遺留分が侵害されている場合は、その侵害されている範囲では持ち戻し免除の効力は失われるため、被相続人に持ち戻しの意思があったとしても遺留分の請求は可能となります。
3-3.遺留分を考慮した範囲での優遇を考える方が望ましい
長男にすべての財産を相続させる、特別受益は持ち戻し免除するといった遺言を残していた場合でも、それが他の相続人の遺留分を侵害してしまった場合は遺留分を請求される可能性が残り、特別受益者である長男は遺留分相当額を金銭で支払う必要があります。
遺留分の問題は紛争化しやすい話になってくるため、弁護士としては、初めから遺留分を考慮したうえで分配を構想するほうが安全策としては望ましいと言えます。
関連:特別受益者にあたりうるのはどこまでの範囲か?
特別受益を受けた人のことを特別受益者といいます。
相続が発生した際に、実際にどこまでの範囲が特別受益者として含まれるのかについては、一般的に以下のような人達であると言われています。
・推定相続人
相続が開始された際に遺産を相続することが推定される人のこと。
被代襲者(被相続人よりも先に死亡した推定相続人)がいる場合、被代襲者も特別受益者に含まれます。
・代襲者
贈与を行った時期によっては、特別受益者に含まれることがあります。
・相続人の配偶者または親族
相続人の配偶者や親族が特別受益者になることは基本的にありませんが、名義は配偶者や親族になっているのに、実際に贈与を受けた人は別の人である場合などには、特別受益者に含まれることがあります。
・推定相続人になる予定の人
被相続人が、養子縁組をする予定の人など、推定相続人になる予定の人に贈与を行うことがあります。
推定相続人になる前に行った贈与に関しては、特別受益かどうかが贈与を行った動機により判断されます。
4.実際に遺留分を請求するには
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分侵害額請求を行うことで自身の最低限の相続分を請求することができます。
この請求ができる相続人は、直系尊属、配偶者、子及びその代襲相続人のみです。
例えこの中の1人が遺留分の放棄を行ったとしても、他の相続人の遺留分が増えることはありません。
また、遺留分侵害額請求には、遺留分侵害の事実を知った日から1年、もしくは相続開始から10年という期限があります。
この請求期間を過ぎると、基本的に請求権が失われてしまうので、必ずこの期間内に請求をするようにしてください。
補足:旧「遺留分減殺請求」から遺留分侵害額請求になり大きく何が変わったのか?
遺留分の請求をする方法として、かつては「遺留分減殺請求」という形で、遺贈や贈与の効力を一部取り消すような手続が中心でしたが、2019年の民法改正で「遺留分侵害額請求」に変わり、金銭請求が原則化されました。
制度の変更に伴い、遺留分や特別受益の金額をめぐる争点は「どれだけ金銭で補填すれば遺留分が満たされるか」という点にシフトしています。
遺留分請求には遺言内容や特別受益有無、特別受益者の資力など、複合的な検討が必要になりますので、できるだけ早期に弁護士へ相談して遺留分請求の可否や方針を定めてもらうことがよいでしょう。
5. よくある質問Q&A
Q. 生前贈与がいつ行われたかで特別受益の結論は変わる?
原則として、相続開始前1年以内の贈与は遺留分計算に入るなどのルールがありますが、特別受益に該当すれば10年以上前の贈与でも計上される場合があります。最終的には「本当に相続分の前渡しに当たるか」が争点となります。
Q. 兄弟間で大きな収入格差がある場合の考慮点
遺留分自体は“生活困窮”ではなく“法的に最低限保証される取り分”なので、たとえ兄弟の収入差が大きくても、特別受益の有無や遺留分計算自体には基本的に影響しません。
ただし、話し合いで収入状況を踏まえて調整することは可能です。
Q. 特別受益は一部だけ認定されることもある?
当事者間で主張が食い違う場合、「一部は特別受益、残りはそうでない」と判断されることもあります。
その結果、最終的な遺産総額に部分的に加算され、遺留分侵害額が減少または増加する形で決着します。
6.本コラムのまとめ:特別受益を踏まえた遺留分請求は弁護士のサポートを
特別受益をめぐる遺留分請求は、相続トラブルのなかでも特に複雑な部類に入ります。
生前贈与の時期や金額、特別受益にあたるかどうかなど、争点は多岐にわたります。
また、遺留分を主張する立場だけでなく、遺留分を請求された立場でどのような対応が必要なのかというのも法的な知識が十分でないと対応が難しいでしょう。
遺留分の請求には期限がありますので、期限内での対応を行わなければなりません。
「これは特別受益に該当するのか」「兄弟にすべての財産を相続させるとなっているが自分は一切もらうことができないのか」など、相続人の間での不公平感を感じておられる方は、できるだけ早めに弁護士にご相談ください。