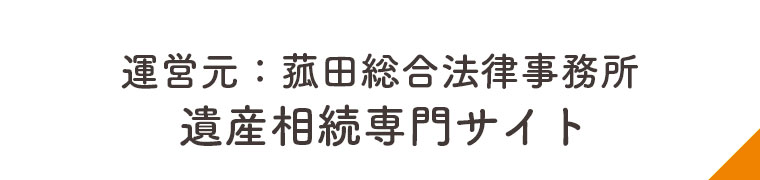相続人の中に認知症の人がいる場合はどうしたらいい?~成年後見制度の基礎から手続きの流れまで詳しく解説~
動画でわかりやすく解説!
はじめに
今や日本で認知症を患っている人の数は、2012年時点で約462万人、65歳以上の高齢者の約7人に1人が認知症と言われ、2025年には高齢者の4人に1人が認知症になると考えられています。
年々増え続けている認知症患者ですが、被相続人が亡くなり、相続をすることになったとき、相続人の中に認知症の人がいたらどうしたら良いのでしょうか?
本記事では、相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議や、法的手続きをスムーズに進めるための手法として「成年後見制度」を中心に解説します。
認知症への対応は誰にでも起こりうる問題です。
ぜひ最後までお読みいただき、将来の相続発生時に備えておきましょう。
1. 相続人の中に認知症の人がいる場合
1-1. 認知症の方が相続人になるとどうなるか
相続人の中に「認知症」の人がいた場合、あなたならどうしますか?
被相続人が亡くなったという事実を認識することが不可能なほど症状が重い認知症であっても、その人が相続人であるということは変わりありません。
遺産分割協議から認知症の人を外すことはもちろんできませんし、認知症である相続人以外の人で行われた遺産分割協議書は無効となります。
つまり、どれほど認知症の症状が重く、自力で法的な判断を下せない状況であったとしても、「法定の相続人」という身分は失われないのです。
これが、後に説明する成年後見制度の重要性につながります。
1-2. 判断能力が不十分でも相続人としての権利はそのまま
上述のように、認知症の人を法的な協議から外すことは許されません。
これは民法上、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるからです(相続人全員での協議を欠いたまま遺産分割協議書を作ってしまうと、協議自体が無効になってしまう)。
したがって、認知症の方の代わりに「法的に有効な意思表示を行える人」を立てる必要が出てきます。これを現行制度では「成年後見制度」が担っています。
1-3. なぜ「成年後見制度」が必要なのか
認知症を患っている方は、判断能力が不十分であるため、何らかの意思表示を行ったとしても法的に無効となってしまいます。
とはいえ、先ほどもお話したように、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、認知症の方を代理する存在が不可欠です。
成年後見制度は、こうした状況で本人の代わりに法律行為(遺産分割協議への参加や財産の管理など)をするために必要になります。
2. 「成年後見制度」とは何か
2-1. 成年後見制度の全体像
「成年後見制度」とは、認知症や、交通事故で植物状態になった場合など、知的障害や精神障害が原因で、十分な判断能力を持っていない方に代わり、成年後見人や保佐人、補助人などの代理人が身の回りの世話をしたり、財産に関する法律行為を代理・同意・取り消したりする制度のことです。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、さらに法定後見制度は「成年後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。
今回のように、認知症をすでに患ってしまっていて判断能力がすでに不十分な場合は、「法定後見」を使うことになります。(任意後見は本人の判断能力がまだ十分に残っているときにしか使えません。)
2-2. 「法定後見制度」の3類型
- 1.成年後見:
十分な判断能力を有していない方が、不利益を被らないよう、家庭裁判所に申立を行い、本人を援助する後見人をつける制度のこと。 - 2.保佐:
精神障害や認知症によって、日常的なことを1人で行うことは可能だが、重要な法律行為を行うことは難しい場合に家庭裁判所が保佐人を選任し、特定の行為や重要な行為に関して代理権・同意権が認められる制度。 - 3.補助:
日常生活に特に問題はないが、本人が1人で行うことが難しい行為がある場合にのみ補助を行う制度。家庭裁判所が定める特定の行為に関して同意権が認められる。
被後見人が「成年後見」「保佐」「補助」のどこに該当するのかは、医師の診断等をもとに、家庭裁判所の審理を経て判断されます。
3. 法定後見制度の手続きの流れ
3-1. 医師の診断書の取得
被後見人が「成年後見」「保佐」「補助」のどれに当たるかを判断するため、重要になるのが医師の診断書です。
- 1.かかりつけ医や専門医 に診断してもらい、判断能力の有無や程度を示した診断書を用意します。
- 2.診断書の作成には本人の社会的・家庭的状況などの情報が求められる場合があるため、事前にケースワーカーや医師と相談して準備するとスムーズです。
基本的に認知症用のテストである長谷川式スケールを実施し、10点未満であれば成年後見相当、15点未満であれば保佐相当、20点未満であれば補助相当と判断されることが一般的です。
3-2. 家庭裁判所での手続き
1.申立:
o申立書、医師が作成した診断書、戸籍謄本、財産目録など各種書類と手数料を用意します。
o申立人は原則として被後見人の配偶者、四親等内の親族などに限られますが、「身寄りがなかったり、親族が申立に協力してくれなかったりして、自分で申立できない状態にあるが、明らかに後見の必要性が高い」というような状況では市町村長が公的保護の一環として代わりに申立を行うこともあります。
2.調査鑑定:
o裁判所が本人の判断能力を詳しく調べたり、状況をヒアリングしたりする場合があります。
3.審判:
o後見開始の審判と後見人の選任が行われます。
誰を後見人とするかは家庭裁判所の判断に委ねられ、親族を選ぶ場合もあれば、専門家(弁護士・司法書士など)が選任されるケースもあります。
4.後見事務:
o後見人が選任されると、その人が本人の財産管理や生活支援を行い、定期的に家庭裁判所へ報告します。
4. 後見人の業務
4-1. 身上監護(生活・介護・医療など)
被後見人が、適切な生活を送ることができるように、介護保険の申請や施設への入退所手続きを行うなど、身の回りのサポートを行うのが「身上監護」の役割です。
- •介護サービスの利用: 介護保険の利用申請や、ケアマネジャーとの連携など。
- •医療・介護施設との契約: 入所・退所の手続き、施設費用の支払い管理。
- •住居の確保: 自宅での生活が難しくなった際の施設探しなど。
4-2. 財産の管理
被後見人に代わって、預貯金の出し入れや公共料金の支払い、場合によっては不動産の売却などの法的手続きも行います。
- •税金や法律手続き: 毎年の確定申告を行ったり、登記申請をしたりする場面も。
- •資産の保全: 不動産の賃貸管理や修繕、株式・投資信託の方針決定など、財産を守るための作業を担います。
- •裁判所の許可が必要な行為: 被後見人の居住用不動産を売却するなど重大な処分を行う際は、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
4-3. 家庭裁判所への報告
後見人は、上記のような身上監護や財産管理の実務を行うだけでなく、その内容を家庭裁判所に対して報告しなければなりません。
指示に応じて定期的に報告書を作成し、どのように財産を管理し、どんな生活支援を行っているかを明らかにします。
5. 「認知症の人が相続人」の場合の実際の対応の流れ
5-1. 成年後見人を立てるまでの手順
相続人の中に認知症の方がいると分かったら、まずは医師の診断書を取得し、法定後見制度を利用して後見人を就けなければなりません。
- 1.認知症の程度を診断してもらう:
判断能力の有無、判断能力が不十分な場合はどの程度なのかを証明してもらいます。
なお、ここで判断能力が問題なくあるという結論になった場合は、後見申立はせずにそのまま遺産分割協議を進められます。 - 2.家庭裁判所への申立:
必要書類(診断書、戸籍、財産目録など)を揃え、後見人を選任してもらう。 - 3.後見開始の審判:
誰が後見人になるか確定。 - 4.遺産分割協議への参加:
後見人が認知症の本人に代わり、他の相続人と協議を行う。
5-2. 遺産分割協議と「同意権・代理権」
成年後見人が就いたら、その後見人が被後見人の利益を守るために、遺産分割協議に参加します。
法定後見人には一定の権限(同意権や代理権)が認められるため、被後見人が判断できない内容については、後見人が本人に代わって適切に意思表示を行うほか、万が一本人に不利益な内容であれば後見人にて同意を拒否することもできます。
なお、遺言書が存在する場合は遺言書の内容での遺産分割を行うこととなりますが、法定相続人には最低限保障される取り分として「遺留分」が認められており、この遺留分を侵害している場合、侵害された相続人は遺留分侵害額請求を行う権利を持っています。
そのため、万が一認知症の相続人の遺留分が侵害されていた場合は、認知症だからといって権利が失われるわけではなく、遺留分請求の意思表示自体を後見人が代わりに行うことになるのです。
6. 認知症の方が相続を放棄する場合の注意点
相続人の中に認知症の方がいる場合、まずは前述の手順で後見人を立て、遺産分割協議に参加してもらうことが基本の流れです。
しかし、財産を相続することで返済の必要な借金を背負ったり、不動産の維持管理に大きな負担がかかったりする場合など、「相続放棄」を選択するほうが本人のためになるケースが存在します。
1.相続放棄手続も後見人が行うこととなる
相続放棄は「相続人がすべての相続財産を受け取らない」と宣言する行為であり、重大な法的効果を伴います。
通常、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならず、期限に遅れると放棄が認められません。
しかし、認知症の方は自力で意思表示を行うことが困難なため、法定後見人による代理が不可欠となります。
2.後見人が相続放棄を検討する理由と条件
後見人は、被後見人の利益を最優先に考える義務を負います。
通常、財産のプラス要素が大きいなら相続放棄は得策ではありませんが、以下のような理由から放棄を選ぶことがあります。
- 1.多額の借金や連帯保証債務が含まれる
被相続人に大きな負債があり、相続すると借金返済義務が発生してしまう場合。 - 2.不動産の管理・維持が困難
老朽化した家屋や遠方の土地を抱え込むことで維持費や税金がかかり、売却も難しいケース。 - 3.ほかの相続人が財産を引き継ぐのが妥当
相続放棄により、事実上ほかの相続人への継承がスムーズになる状況があり、被後見人本人に損がないと判断される場合。
ただし、後見人の独断で安易に放棄を行うと、家庭裁判所から「本当に本人の利益になっているのか?」と疑問を呈される可能性もあります。
たとえば財産のプラス面が大きいにもかかわらず後見人の都合で放棄させたとなれば、不正行為とみなされかねません。
3.相続放棄の流れ(家庭裁判所への申述)
認知症の方の相続放棄を正式に進めるには、まず後見開始の審判で後見人が選任されていることが前提となります。
そのうえで、後見人が「相続放棄を行うことが被後見人にとって最善」と判断したら、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う流れです。
- •後見人による申述書の提出
- •裁判所による審査
- •許可が必要となる場合も
必要書類を揃えて家庭裁判所に提出し、放棄が妥当な理由を説明します。
負債の程度や財産状況、被後見人の生活環境などを総合的に確認し、「放棄が本人のためになる」と認められれば受理されます。
後見人はあくまで被後見人を代理する存在ですが、相続放棄の影響は大きいため、裁判所が追加で質問や補足書類を求める場面もあります。
特に、不動産や金融資産が大きい場合には慎重に審査されることがあります。
4.相続放棄に伴うリスクと注意点
- 1.すべての財産を失うリスク
- 2.期限や書類不備で放棄が認められない場合
- 3.親族間の対立
相続放棄は借金などの負債を免れる反面、プラスの財産も一切受け取れなくなる行為です。
後見人としては、遺産のマイナス面だけでなく、プラス面も正確に算定したうえで結論を出す必要があります。
相続放棄には厳格な期限(3か月以内)があり、後見人の選任に時間を取られると申述が間に合わないリスクもあります。
早期に専門家へ相談して手続を進めることが肝要です。
相続放棄を選ぶことで、他の相続人の中で「本当に本人(認知症の相続人)のためになるのか?」と疑念が生じることもあります。
後見人が透明性をもって事情を説明し、裁判所の監督下で公正に進めていく必要があります。
7. 認知症の相続人に関するよくあるQ&A
Q. 認知症の相続人が施設に入所していても、遺産分割協議に参加させなければならない?
A: 法的には相続人全員が協議に参加する必要がありますが、認知症で施設に入所中の方の場合はすでに判断能力が不十分であるため、後見人を選任して協議に代わり参加してもらう形がとられます。
Q. 親族が「親はまだ認知症ではない」と主張して後見申立に反対しているなら?
A: 後見申立には医師の診断書が必要であり、それを踏まえて家庭裁判所が最終的に判断します。
親族が反対していても、診断書から判断能力が明らかに低下していると認められれば、後見開始の審判が下される可能性が高いです。
親族間の意見対立が激しい場合、裁判所が公正な第三者(弁護士など)を後見人に選ぶことで公正性を担保します。
Q. 相続人が認知症だと知らず、遺産分割協議をして協議書に印鑑を押してしまったら?
A: 判断能力が不十分な状態での遺産分割の実施と協議書の作成は無効となる可能性が非常に高いです。
この場合は遺産分割協議が法的に成立していないこととなるため、再度後見人を就けたうえで協議をやり直さなければなりません。
8. 本コラムのまとめ
今回の記事では、相続人の中に認知症の人がいた場合、どのように遺産分割協議を進めるのか、そして成年後見制度の手続きや後見人の業務について詳しく解説しました。
もし、相続人の中に認知症の人がいる、あるいは今後その可能性がある場合には、まずは「成年後見制度を利用すれば解決できるかもしれない」という前提を頭に置いてみてください。
制度の選択や手続きの進め方について迷ったときは、ぜひ専門家へ相談するのがベストです。
財産管理や身上監護だけでなく、相続税や不動産の名義変更など、法的・税務的な問題が絡む場面も多々あるため、弁護士や税理士、司法書士が連携してサポートできる当事務所であれば、ワンストップですべての相続手続きを進めることができます。
近年は高齢化の進展に伴い認知症のリスクが身近になりつつあります。
相続と認知症は切り離せない課題となっている今こそ、後見制度の活用がスムーズにできるよう情報収集を進めておいて損はありません。
もし具体的な悩みや疑問がある場合は、まずは初回無料相談をご利用ください。