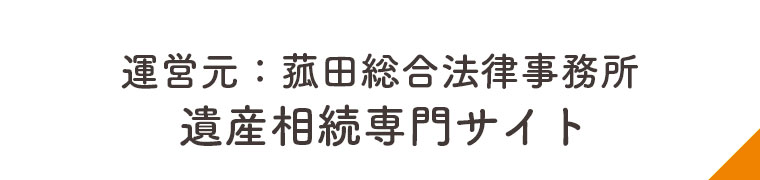任意後見って何?どういうときに使えばいいの?
動画でわかりやすく解説!
「将来、判断力が衰えたときのために備えたい」「親が高齢になり、財産管理や生活面のサポートが必要かもしれない」──そんな思いを抱える方にとって、後見制度は有力な選択肢です。
本記事では、任意後見と法定後見の仕組みや手続き、メリット・デメリットを弁護士としての視点を交えつつわかりやすく解説します。老後やご家族の将来に不安を抱える方は、ぜひ最後までご覧いただき、必要に応じて無料相談のご利用を検討してみてください。
1. 後見制度とは?
1-1. 後見制度の概要
認知症やその他の病気によって判断能力を失うと、不動産の売却や預貯金の引き出しといった財産の管理や処分、あるいは日常生活に必要な契約ごと(たとえば施設入所の手続きなど)等の重要な手続きを本人だけで行えなくなってしまいます。また、不審な勧誘を受けて詐欺被害に遭ってしまうなど、普段の生活をする上でのリスクも高まってしまいます。
このようなリスクを回避する方法として、本人に代わって財産管理や契約手続きを行うための法的枠組みが「後見制度」です。
後見を利用すれば、後見人(または後見受任者)が本人に代わって契約や財産管理を行えるほか、トラブルを未然に防ぎやすくなるのが大きなメリットです。
1-2. 任意後見と法定後見の位置づけ
後見制度には、**自分の意思で契約を結んで準備する「任意後見」**と、**家庭裁判所が後見人を選び、法律の枠組みで支援する「法定後見」**の二つがあります。どちらも本人の生活や財産を守る制度ですが、選べる時期や自由度が異なるため、まずは両者の仕組みと違いを知ることが重要です。
2. 任意後見と法定後見の違い
2-1. 任意後見とは?
「任意後見」とは、今はまだ十分な判断能力を有している方が、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、後見人となるべき人を選んで、「その人に、どの程度の権限を委ねるか」を契約で決めておく仕組みです。(この契約を、任意後見契約とよびます。)
「任意後見契約」は、必ず公正証書で締結し、将来、認知症などにより判断能力が不十分となったときには、この契約にもとづき、「任意後見人」が被後見人の補助を行います。任意後見は、本人の意思に基づいて後見人を選ぶことができるため、自分で信頼できる人を事前に選定できるという利点があります。ただし、判断能力が低下した後に契約を結ぶことはできないため、タイミングを逃すと利用が難しくなる点には注意が必要です。
2-2. 法定後見とは?
一方、法定後見は、すでに判断能力が衰えてしまった後に、家庭裁判所が後見人(あるいは保佐人、補助人)を選任する制度です。「後見・保佐・補助」という三つの類型があり、判断能力の程度に応じて家庭裁判所が適切な類型を決定します。たとえば、財産の管理能力がほぼ失われている場合は「後見」、一部サポートがあれば判断できる場合は「保佐」や「補助」を選ぶ、といった流れです。法定後見の場合は本人の意思で後見人を自由に決めることはできないため、そこが任意後見との大きな違いです。
関連:「任意代理契約」とは?
任意後見に関連して、「任意代理契約」というものについても簡単にご紹介します。
「任意代理契約」とは、「財産管理契約」とも呼ばれ、1人暮らしの高齢者の方などが、判断能力は有しているものの、ご自身で金融機関などに行って手続きを行ったり、財産管理を行うことに不安を覚えたりした場合などに、ご家族や弁護士など、自分で選んだ信頼のできる人と個別の任意契約を結び、財産管理やその他生活の中での手続きなどを任せるものです。
任意代理契約を利用すると、公正証書によって契約を締結した代理人が財産の管理や、年金の管理などを行います。そうすることで、被後見人ご本人の財産を、ご家族やご親族による使い込みや詐欺、悪徳商法などから守ることができるのです。
「財産管理契約」と「成年後見・任意後見」との違いとしては、財産管理契約は契約締結後すぐに効力が発生するということが挙げられます。(成年後見や任意後見の場合は、契約者ご本人の判断能力の低下が効力発生の条件となっています。)
また、ほとんどの場合、「財産管理契約」を行う際に、「将来、認知症などによって判断能力が低下した際には、任意後見に移行する」といった契約も一緒に締結します。
なお、「財産管理契約」の内容については、当事者間の合意によって決めることが可能で、開始する時期も自由に決められることになっています。
3.「任意後見契約」の具体的手続
3-1.任意後見人決定から後見業務開始までの流れ
任意後見契約を締結してから、実際に任意後見契約を利用するとなったときの流れは以下のようになります。
任意後見人の決定
↓
任意後見契約の締結
↓
ご本人の判断能力の低下
↓
任意後見監督人の申し立て
↓
任意後見監督人の選任
↓
後見業務の開始
このように、任意後見契約を結んだ後に、認知症などによって判断能力が不十分となった場合には、あらかじめ任意後見契約を結んでいた後見人が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。そして、任意後見監督人が選任されると同時に、任意後見開始となります。
任意後見契約を締結していれば自動的に後見業務が開始されるわけではないので留意しておきましょう。
参考:「任意後見監督人」とは?
さきほど任意後見監督人という言葉がでてきましたが、これは、任意後見人が行う事務業務の監督を行ったり、その事務に関して家庭裁判所に定期的に報告を行ったりする人のことです。
任意後見においては、被後見人が後見人を自由に選任できる一方、本人が後見人からいいように利用されてしまうリスクがあることから、後見人を監督する立場として家庭裁判所が選任します。
3-2.任意後見人に選べる人はどのような人か?
原則として、被後見人が自由に任意後見人となる人を選ぶことができますので、ご自身が自分の代わりに手続きを任せたいと思う人を選定して構いません。
ただし、法的に後見人に不適任とされる、以下に該当するような方については、後見人となることができません。
・未成年者
・破産者
・行方不明者
・家庭裁判所によって後見人を解任された法定代理人、保佐人、補助人
・本人(被後見人)に対して、訴訟を行った者、及びその配偶者、直系血族
・不正な行為や著しい不行跡など、任意後見人の任務に適さない事由がある
3-3.任意後見人には誰を選ぶべきか?
実際問題として、任意後見人に誰を選任すべきなのかというのは皆さん気になられるかと思いますが、さきほどお伝えしたように一部法律で制限があるものの、基本的には自由に選んでもらってよいです。
ただ、本人の財産を適正に管理する、後の親族間トラブルを防ぐ、という観点から見ると、弁護士等の専門家を選任するのが無難ではあります。
弁護士への依頼を考えられている場合は、任意代理契約を利用して判断能力低下前の財産管理から依頼をしておかれると、実際の後見業務開始までに自分が希望する財産管理方法を共有でき、弁護士にも自分の要望を把握してもらえるため、判断能力が低下してしまった後もスムーズに対応が進められるかと思います。
4. 法定後見の具体的手続
4-1. 法定後見の種類とは?(後見・保佐・補助の3類型)
法定後見には、後見・保佐・補助の三つの類型があり、判断能力の程度に応じて選択されます。類型の決定は裁判所が行いますので、こちらで任意の類型を指定することはできません。
後見: 判断能力がほとんど失われている
保佐: 判断能力が著しく不十分だが、一部は自力で判断できる
補助: 判断能力が不十分な部分が限定的
4-2. 法定後見を利用するための流れ
法定後見を利用するには、家庭裁判所に申立書と医師の診断書、財産目録など必要書類を提出します。申立人には配偶者や四親等内の親族などの制限があり、申立にかかる費用(印紙代、郵便切手、医師の鑑定費など)も発生します。家庭裁判所の審理を経て選ばれた後見人は、本人の財産管理や契約行為を代理する権限を持ちます。
4-3. 後見人の権限と義務
法定後見人は、家庭裁判所の監督を受けながら、被後見人(本人)の利益を最優先に行動する義務を負います。預金口座の管理や日常生活に必要な契約行為を代行することはもちろん、被後見人が不利益を被らないよう細心の注意を払い、定期的な報告書を家庭裁判所に提出しなければなりません。
ただし、後見人が不動産の売却など重大な処分行為を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。これは、後見人が被後見人の財産を独断で処分することを防ぎ、あくまで「被後見人にとって必要かつ適切」な行為だけが認められるようにするための制度です。賃貸借契約や自宅の売却のような財産価値の大きな取引を行う際は、必ず許可手続を経て、本人の生活に悪影響が出ないことを確認する仕組みとなっています。
また、法定後見人が無報酬というわけではなく、財産規模や業務量に応じた報酬が認められる場合が少なくありません。後見人に就任する際は、家庭裁判所へ申立てを行い、適正な報酬額を決定してもらうのが一般的です。後見業務は本人の財産管理から医療・介護に関する契約行為まで多岐にわたるため、活動範囲や責任に見合った報酬が設定される仕組みといえます。
5. どちらを選ぶ?任意後見と法定後見の使い分け
5-1. 判断能力があるうちに準備できるメリット
任意後見は、将来への備えとして判断能力がある段階で契約を結べるため、「この人にお願いしたい」「こういう場面で助けてほしい」といった本人の希望を色濃く反映させられます。一方、法定後見は「すでに本人が十分な判断能力を持たない」状態での最後の手段として利用されるケースが多く、家庭裁判所の裁量が大きい点が特徴です。
5-2. 家族の納得度の得やすさ
特に財産管理や財産処分をめぐって親族間で対立しやすい場合は、あらかじめ任意後見を結んでおくことで家族の納得を得やすいかもしれません。法定後見だと、後見人の選任が裁判所主導で進むため、「知らない第三者が来てしまった」という戸惑いが生じやすいとも言われます。
5-3. こんな人には任意後見・こんな人には法定後見
任意後見に向く人
任意後見は、「どの財産をどう管理してほしいか」「医療・介護の契約をどこまで委ねるか」といった具体的な希望を事前に取り決められるため、「自分が信頼する弁護士や親族に管理を委ねたい」「資産運用や医療方針などの希望を明確にしておきたい」という方に向いています。本人が元気な段階で手続きを進める必要があるため、早めに将来の備えをしたいと考える人が利用しやすいのが任意後見の大きな特徴です。
法定後見に向く人
法定後見を選択する大きな理由としては、すでに本人の判断能力が十分でなく、本人自ら任意後見契約を締結することが難しい場合が挙げられます。また、家族内で「誰が財産管理を担当するか」合意できないケースや、適任と思える親族がいないときにも、家庭裁判所を通じて後見人を選ぶ法定後見の仕組みが有効です。こうした状況では、裁判所が専門家や第三者を後見人として選任し、中立的な立場で財産や生活面の管理を行ってもらうほうが、本人にとって安心かつ公平なサポートにつながりやすいでしょう。
6. 本コラムのまとめ:万が一のリスクに備えて早めの対策をしておきましょう
任意後見と法定後見はいずれも、将来の判断能力低下を見据えてご自身の財産を適切に管理するための大切な制度です。もし「どちらが自分や両親に合っているのか分からない」「いつまでに何をすればいいのかイメージできない」という悩みがあれば、まずは専門家への相談が近道です。
当事務所では、弁護士だけでなく税理士や司法書士も含む総合的なグループ体制を強みとしており、任意後見契約のサポートから法定後見申立、その他生前対策を含めて相続全般をワンストップで対応可能です。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。