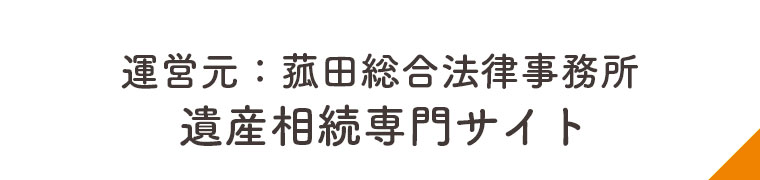弁護士が解説する「遺言書の作成方法」|失敗しない手順と専門家活用のポイント
- HOME
- お悩み別コラム
- 遺言書を作成したい・遺言執行者を選任したい
- 弁護士が解説する「遺言書の作成方法」|失敗しない手順と専門家活用のポイント
「遺言書を作りたいけれど、具体的にどう進めればいいのか分からない」「自分だけで作成して大丈夫か不安」という方は多いのではないでしょうか。遺言書の作成方法にはいくつかの形式があり、それぞれメリットや手続きの流れ、必要となる費用などが異なります。そして、不正確な書き方や保管方法の問題が原因となり、せっかくの遺言書が無効になってしまうケースも少なくありません。
本記事では、弁護士として数多くの相続相談に携わってきた視点から、遺言書の作成方法に関する基本的な知識や手順、意識しておきたい注意点をわかりやすく解説します。
1.遺言書を作成すべき理由:なぜ必要とされるのか?
「自分はまだ若いから遺言書は必要ないのでは」「家族間でトラブルは起きないだろう」という声はよく耳にします。しかし、人生は何が起こるか分からないもの。万が一に備えて、以下のような観点からも遺言書の作成は検討すべきといえます。
相続させる割合を任意で指定できる
民法上は、相続人の地位に応じて法定相続分という一定の割合が決められていて、相続が発生した際はこの法定相続分に沿って遺産分割を実施するのが基本ですが、遺言書を用いることで個別の事情を踏まえた任意の割合での分配を指示できます。
相続人以外への遺贈ができる
お世話になった方や施設、慈善団体など、法定相続人でない人へ財産を渡したい場合、遺言書がなければ実現困難なケースがほとんどです。
円満相続の実現
事前にきちんとご自身の意思表示を残しておくことで、相続人同士の紛争を防止できる可能性が高まります。
相続税対策・紛争防止
相続税の対策や、遺留分対策を含めた遺言書作成を行えば、後々のトラブルリスクを軽減できます。
2.遺言書作成の基本手順
遺言書を作成するためには、主に以下の流れを意識して進めるとスムーズです。これらの手順で進めることで、形式的にも内容的にも齟齬のない遺言書を作りやすくなります。
2-1.目的の明確化
はじめに「なぜ遺言書を作成するのか?」という目的を明確にしましょう。たとえば「不動産を長男に相続させたい」「配偶者に多めの財産を残したい」「特定の遺産を特定の相続人に遺贈したい」など、具体的な目的がはっきりすると、作成方法や遺言書の種類を選ぶ際にも指針が立てやすくなります。
2-2.遺産と相続人の確認
次に、遺産と相続人を正確に把握する必要があります。遺産としては、不動産、預貯金、株式・投資信託などの金融資産、負債(住宅ローンなど)も含めた全体像の確認が重要です。相続人の範囲は民法によって定められており、配偶者や子、親、兄弟姉妹など、どの順位で相続権が発生するかを理解しておく必要があります。特に相続人が複数いる場合、遺留分(民法上で定められた最低限の遺産の取り分)にも注意を払いながら分配案を検討しなければなりません。
2-3.遺言書の形式選択
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの主要な作成方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。自筆証書は費用が安くて手軽ですが、保管や書式不備に気を付ける必要があります。一方、公正証書は公証人が作成に関与してくれるため安全性が高いものの、手数料がかかります。秘密証書は内容を秘密にしたまま公的な証明を得られる反面、あまり利用されることが多くないのが現状です。どれを選ぶかは財産内容や相続人の状況、必要な費用や変更頻度などを踏まえて判断します。
2-4.内容の起案・専門家への相談
形式を決めた後は、実際に遺言書に書くべき内容を起案します。ここでは分配方法だけでなく、遺言執行者の指定や付言事項なども含めて検討するとよいでしょう。付言事項とは、法的な効力は持たないものの、遺言者のメッセージや想いを伝えるための文章で、円満相続のために有効な場合があります。内容を作成したら、専門家に一度相談し、法的リスクや税務リスクのチェックを受けることをおすすめします。
2-5.署名・押印・保管
最終的に遺言書を完成させたら、署名や押印、適切な保管が重要です。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、保管場所を十分に検討したうえで管理するか、自筆証書遺言の場合は法務局保管制度を利用するのがおすすめです。公正証書遺言であれば原本が公証役場に保管されるため安全性は高いですが、遺言書の存在を相続人にきちんと知らせておくなどの配慮も必要です。
3.遺言書の主な作成方法と特徴
ここでは、実際に遺言書を作成するうえで代表的な3つの方法と、併せて知っておきたい法務局保管制度について、その手順や特徴を解説します。
3-1.自筆証書遺言の作り方
自筆証書遺言は、遺言者が自ら紙に全文を手書きし、日付・署名・押印を行う形式の遺言書です。費用がほとんどかからず、思い立ったときにいつでも作成・書き直しができる点が大きな魅力です。ただし、以下のポイントに注意が必要となります。
全文を直筆する必要がある
パソコンでの作成や一部代筆は認められません。何らかの事情で手書きで長文を書くことが難しい場合などは、自筆証書遺言の形式での作成が難しくなるケースがあります。
法律で決まった要件・書式を厳守する
少しでも要件を満たしていない場合は遺言書が無効になります。日付の漏れや署名漏れなど、注意をして作成が必要です。
紛失や改ざんのリスクがある
自宅保管をする場合、火災や盗難、あるいは故意による破棄などのリスクが否めません。
3-2.公正証書遺言の作り方
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成を依頼する方法です。証人2名以上の立会いが必要になりますが、作成過程で公証人が内容を確認し、形式面での不備が生じにくいという安心感が得られます。主なメリットと注意点は下記の通りです。
形式不備のリスクが少ない
法律の専門家である公証人が適切に書面化してくれるため、形式不備のリスクは低いです。また、遺言内容を自筆する必要もありません。
原本は公証役場で保管される
作成した遺言書は公証役場で保管をされるため、紛失や改ざんの心配がほとんどありません。また、公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続が不要ですので、スムーズに遺言執行手続に移ることができます。
費用がかかる
公正証書遺言を作成する場合は、公証役場に支払う手数料、証人を公証役場で手配する場合はその手数料などが発生します。頻繁に書き直す場合は、費用がかさむ点に留意が必要です。
3-3.秘密証書遺言の作り方
秘密証書遺言は、自筆証書と同様に遺言者が内容を作成しますが、その遺言書を封印した状態で公証人と証人に証明を受ける形式の遺言書です。特徴は以下の通りです。
遺言の内容を秘密に保てる
公証人や証人は書面の内容を確認しないため、遺言の具体的な分配内容を知られたくない方に向いています。
形式不備の可能性がある
遺言書自体の内容は本人で作成する必要があり、内容を開示しないため不備があった場合でも公証人による指摘は入りません。
検認手続が必要
自筆証書遺言と同様に、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所での検認が必要となるため、相続人側の手続負担は公正証書遺言より大きくなります。
3-4.【補足】自筆証書遺言の法務局保管制度の活用
自筆証書遺言で特に問題となるのが「紛失や改ざんリスク」「死後の検認手続」ですが、2019年の法改正により、法務局に自筆証書遺言を預けられる制度がスタートしました。法務局に預けておけば、遺言書の検認手続が不要となり、相続人の負担を軽減できます。加えて、紛失や改ざんのリスクを大幅に減らせるため、自筆証書遺言を選ぶ場合は積極的に活用してみる価値があります。
4.遺言書作成のタイミングはいつがいい?
遺言書は作成方法だけでなく、「いつ作るか」というタイミングも重要です。
4-1.高齢になってからでは遅い?
一般的に「遺言書は高齢になってから作るもの」というイメージがありますが、判断能力がしっかりしているうちに作成しておくほうが望ましいです。認知症などで判断能力に問題がある状態だと、せっかく作った遺言書が無効とされるリスクも高まります。また、高齢になるほど健康状態に変化が生じやすく、書き直しや専門家とのやり取りが難しくなるケースもあります。
4-2.ライフイベントと見直しのポイント
結婚、離婚、子どもの誕生や独立、財産状況の大幅な変化など、大きなライフイベントが起きた際には、遺言書の内容を見直す機会です。たとえば、配偶者と離婚した場合、遺言書の中でその配偶者への遺贈が記載されていたら修正が必要となるでしょう。若いうちから遺言書を作成しておく場合、公正証書遺言の場合は書き直しの費用がかかるため、自筆証書遺言を選ぶ方が柔軟に対応できるケースもあります。
作成時のポイント①:遺留分・特別受益・寄与分を踏まえた遺言書作成
相続では、遺言書にどのような財産分配を記載しても自由と思われがちです。しかし、遺言書によって一部の相続人の取り分が大幅に減少した場合、いわゆる「遺留分」を侵害している可能性があり、紛争に発展しかねません。加えて、生前贈与を受け取った相続人の特別受益や、高齢の親の介護に尽力した相続人の寄与分をどう評価するかなど、実際の相続を想定し、遺言書を作成するうえで意識しておきたいポイントを整理します。
遺留分の基礎知識と注意点
遺留分とは、民法上の相続人(主に配偶者や子、直系尊属)に最低限保障される取り分のことです。遺言書の内容が遺留分を大幅に下回ると、該当の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。結果として、遺言者の意図した分配が覆される事態にもなり得るため、あらかじめ遺留分を考慮したうえで作成することが大切です。
特別受益・寄与分が相続に与える影響
特別受益とは、たとえば結婚資金や住宅資金の援助、生前贈与など、他の相続人と比べて多額の利益を受けているケースを指します。相続時には、この特別受益を含めて財産総額を再計算するため、遺言書での指定だけでは調整が難しい場面があります。一方、寄与分とは、被相続人の事業を手伝ったり、長期にわたり介護を行ったりして財産維持に貢献した相続人を、公平に評価するための制度です。こうした事情を把握せずに遺言書を作成すると、不公平感から相続人間で深刻な対立を招きやすくなります。
遺留分・特別受益をめぐるトラブル事例
遺言書で特定の相続人に不動産や預貯金を集中させた結果、他の相続人が「遺留分を侵害された」として法的手段に訴え、訴訟に至るケースがあります。また、生前に多額の援助を受けていた事実を隠して遺産分割協議を行い、後になって特別受益として扱われるべき金額が発覚し、協議がやり直しとなる事例も少なくありません。いずれの場合も当初の遺言者の意図が叶わないばかりか、相続人の関係が深刻に悪化する可能性がある点が問題です。
トラブルを回避する遺言書の書き方と専門家の活用ポイント
まずは、ご自身の財産状況と相続人の立場を正確に洗い出し、遺留分や特別受益・寄与分がどの程度影響を及ぼしそうかを確認しましょう。もし、ある特定の相続人に厚く分配したいのであれば、遺言書にその理由を付言事項として記載しておくなど、配慮と説明が重要になります。加えて、弁護士に相談し、事前に各種リスクを把握することで、余計な紛争を回避しつつ意図を最大限に反映できるようになります。特に遺留分を考慮したうえで遺言書を作成しておくことで、後の紛争リスクを下げることができます。
作成時のポイント②:二次相続・事業承継を見据えた遺言書作成
相続は一度終わればそれで完結と思われがちですが、親が亡くなった後に続けてもう一方の親も他界することで発生する「二次相続」も見据えておかないと、結果的に相続税の負担が増大する恐れがあります。また、家業を継ぐ“事業承継”が絡むケースでは、不動産や株式など、対象となる資産の評価や承継方法を慎重に検討する必要があるでしょう。ここでは、二次相続と事業承継を踏まえた遺言書作成のポイントを解説します。
二次相続で相続税が増える理由と節税策
第一次相続で父親、続いて第二次相続で母親が亡くなる場合を例に考えてみると、相続税の総額が大きく変わる可能性があります。なぜなら、第一次相続で配偶者(母親)に多くの財産を集中させると、母親が亡くなった際にその財産の大半が二次相続の対象となり、大きな相続税課税が生じるからです。 そのため、第一次相続時から二次相続を見越したうえで財産分配を行い、配偶者ではなく子へ部分的に財産を移しておくなどの工夫が必要になります。具体的には、以下のような方法が考えられます。
生前贈与の活用
基礎控除額などを上手に使いながら、子や孫に財産を少しずつ贈与しておくことができます。
配偶者控除を必要以上に使わない
相続税の配偶者控除は非常に大きいものの、それによって配偶者に資産を集めすぎると、二次相続時の課税がかえって増すリスクがあるので、注意が必要です。
遺言書で分割方法を調整する
「配偶者にすべてを渡す」形に固執せず、ある程度バランスよく財産を振り分けることで、将来的な納税負担の平準化を狙うことも1つの選択肢です。
このように二次相続を見据えてこそ、遺言書は相続税対策としても効果を発揮します。弁護士と税理士が連携してシミュレーションを行えば、納税資金の確保方法や財産分割の最適解を見つけやすくなるでしょう。
親族内事業承継時における遺言書の活用法
家業を継ぐ“事業承継”が絡むケースでは、代表者の地位や会社の株式、不動産など事業に不可欠な資産をどう扱うかが大きな問題になります。親族内承継を希望する場合は、特定の後継者に株式を集中的に相続させる必要がある一方、他の相続人の取り分や遺留分をどう調整するかが課題となります。 遺言書を通じて「後継者には会社株式を優先的に渡す」「かわりに他の相続人には別の財産を配分する」といった形で役割分担を明確にしておくと、承継がスムーズです。たとえば、不動産を後継者以外の子に与えたり、預貯金や保険金を後継者以外に多く与えたりするなど、相続人間の不公平感を最小化する工夫が必要となります。 また、後継者が事業を円滑に引き継げるよう、経営権だけでなく必要な設備や資金面のサポート体制も意識する必要があります。遺言書と合わせて「死後事務委任」や「遺言執行者の指定」を行い、経営に関わる手続が円滑に進むよう準備しておくと安心です。
事業承継税制のポイントと税理士連携の必要性
事業承継税制は、一定の要件を満たせば事業用資産や株式の相続税・贈与税を大幅に軽減できる制度です。要件の一例として、後継者が会社の代表に就任し、一定期間その株式を保有し続けるなどの条件があります。この制度適用には細かな手続や計画書の提出などが求められるため、専門的な知識が必要です。税理士と連携しながら計画を策定し、遺言書に事業承継に関わる内容を組み込むことで、法的根拠と税務的メリットを両立した対策を打ち出せます。
二次相続を踏まえた資産配分の考え方
二次相続と事業承継が重なる場合、さらに配分の難易度は上がります。たとえば、第一次相続で配偶者にほとんどの会社株式を取得させても、配偶者が亡くなる際の二次相続で後継者が多額の相続税を負担する事態が起こり得るからです。 遺言書の作成にあたっては、まず「一度目の相続でどれだけ配偶者に渡すか」「後継者となる子に株式をどれだけ集中させるか」「余剰財産を他の相続人にどう割り振るか」といった観点から、納税資金の見通しを立てることが重要です。家族構成や事業規模、会社の経営状況によってベストな配分は変わりますが、弁護士・税理士のサポートを受けることで税制を踏まえたうえで無理なく長期的視点に立った遺言書を作ることが可能です。 複数の相続や事業承継に関わる問題は複雑になりがちですが、早めに計画を立てれば、円満な財産承継や節税効果を十分に狙えます。遺言書を通じて「誰が何をどのように受け継ぐのか」を明確に示しつつ、将来の経営を見据えた後継者支援の方法を用意しておくことこそが、家族と事業を守る最善の方法です。
5.遺言書作成における専門家の役割と費用
遺言書自体はご自身でも作ることはできますが、専門家を活用することでトラブルのリスクを最小限に抑えられます。特に複雑な財産構成や相続人関係がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
5-1.弁護士に依頼するメリット
弁護士に相談すると、法的要件の確実な把握だけでなく、万が一の相続争いを見据えたアドバイスが得られます。たとえば、遺留分を巡るトラブルが生じそうな場合、あらかじめ遺言書の書き方や付言事項の記載を工夫し、相続人間の紛争を回避する対策を講じることが可能です。さらに、弁護士は遺言執行者としても就任できるため、遺言者が亡くなった後の手続一式をスムーズに代行してくれます。
5-2.相続税の観点での税理士の必要性
相続が発生すると、場合によっては相続税の申告や不動産の相続登記が必要になります。財産の評価額が大きい場合、税務面での観点を踏まえて遺言書で定める遺産分割案を作成しないと、思わぬところで税負担が増えてしまうリスクがあります。相続税申告時の特例や二次相続まで考慮した遺言内容の作成ができるとベストです。
5-3.専門家費用はどれくらいかかる?
弁護士費用は事務所によって変動しますが、「遺言書作成のサポート」「遺言執行者の就任」「遺言に関連するコンサルティング」といった業務範囲に応じて料金が設定される場合が多いですので、初回相談時に確認をされてみてください。
6.相続LOUNGEならではの強みとワンストップサポート
相続LOUNGEでは、弁護士・税理士・司法書士が相続に関するあらゆる業務に対応しています。遺言書の作成から遺産分割協議、相続税申告、不動産登記まで、一貫したワンストップサービスを提供できるのが最大の強みです。
6-1.相続特化のサポート体制
相続LOUNGEは相続分野に特化した専門家が相談対応を行い、遺言書作成や遺言執行、紛争解決など、多数の事例を通してノウハウを蓄積しています。相続トラブル防止の観点から、遺言書に入れるべき文言や構成を丁寧にアドバイスするのはもちろん、将来的に紛争になった場合でも、当事務所が代理人として迅速に対応できる体制を整えています。
6-2.税理士・司法書士による相続関連業務の一元化
相続においては、税理士法人や司法書士法人との連携が不可欠ですが、相続LOUNGEにはそれらの専門家が在籍しているため、別々に事務所を探す必要がありません。具体的には、相続税申告や贈与税申告、相続登記などもワンストップで行えるため、お客様の手続負担が大幅に軽減されます。
6-3.遺言執行や死後事務委任にも対応
作成した遺言書を実際に執行する「遺言執行業務」にも対応しています。遺言執行者の指定は、遺言書の内容を実現するうえで非常に重要ですが、専門家を選任しておくと相続人間の負担やトラブルリスクが減ります。また、「死後事務委任」として、ご自身が亡くなった後の各種手続(葬儀手配、遺品整理、役所手続など)を生前に定めておくことも可能です。こうしたサービスを組み合わせることで、残された方々への負担を最小限に抑えられるのも相続LOUNGEの特徴といえます。
7.遺言書の作成方法で迷ったときにすべきこと
いざ遺言書を作成しようとすると、「自分に合った形式はどれか」「どんな費用がかかるのか」「相続税は大丈夫か」といった不安や疑問が次々に湧いてくるものです。そんなときには、ひとりで悩まず専門家へ相談するのが最適です。
無料相談のメリット
相続LOUNGEでは初回無料相談を行っており、土曜・日曜含めてご相談をお受けしております。初めての方ほど、漠然とした疑問や不安を抱えているケースが多いので、「どのような手順で進めるのか」「費用感はどれくらいか」「そもそも遺言書が必要なのか」という部分についても、弁護士がしっかりとご説明します。
問い合わせのタイミングは早いほど安心
「まだ大丈夫だろう」と思って先延ばしにすると、思わぬタイミングでトラブルや病気が発生し、遺言書作成が難しくなる可能性も考えられます。判断能力に問題が生じると、遺言書自体が無効になるリスクが高まるため、元気なうちから準備を始めることがベストです。少しでも将来に不安を感じたら、早めの相談をおすすめいたします。
8.本コラムのまとめ:正しい作成方法で将来を安心に
遺言書は、将来の相続を円滑に進めるための非常に大切な書類です。しかし、その形式や書き方を一歩間違えると無効になったり、想定外の紛争や税負担を引き起こしたりするリスクもあります。
だからこそ、正しい知識を身につけ、必要に応じて専門家のサポートを受けながら、将来を見据えた準備を進めることが大切です。
相続LOUNGEでは、相続にまつわるあらゆる手続・問題解決を一括してカバーできる体制を整えています。遺言書作成だけでなく、それ以外の生前対策などを含めて総合的な相続サポートを行っておりますので、トラブルを事前に防ぎ、より円満な相続を実現したいとお考えの方はまずは初回無料相談をご活用ください。