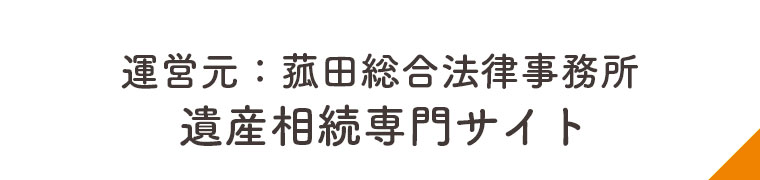【弁護士が解説】あなたに合った遺言書の種類とは?公正証書・自筆証書・秘密証書の特徴と選び方
- HOME
- お悩み別コラム
- 遺言書を作成したい・遺言執行者を選任したい
- 【弁護士が解説】あなたに合った遺言書の種類とは?公正証書・自筆証書・秘密証書の特徴と選び方
「遺言書を作りたいけれど、自分にはどの種類が合っているのだろうか?」──このような悩みを抱えている方は少なくありません。実際、遺言書には複数の種類があり、それぞれ特徴や作成方法、メリット・デメリットが異なります。こうした違いを正しく理解し、自分に最適な遺言書を作成することが、将来の相続トラブルを防ぎ、円滑な相続手続を実現する大きなカギとなります。
本記事では、弁護士として実際に多くの相続案件を取り扱っている立場から、遺言書の種類と選び方についてわかりやすく解説します。
1.遺言書はなぜ重要なのか
遺言書は、自分の財産をどのように分配するかを明確に示すだけでなく、残されたご家族や関係者の負担を大幅に減らす重要な文書です。遺言書がない場合や内容が曖昧な場合、相続人同士の意見が対立して相続手続が進まず、結果的に長期間にわたる紛争へと発展するケースも珍しくありません。
特に高齢化が進む現代では、相続に関するトラブルの複雑化や増加が社会問題化しています。そのような背景から、遺言書を作成する方は増加傾向にあります。ただし「書き方に自信がない」「公正証書にしたほうがいいのかよくわからない」という悩みも多く、どの種類を選ぶべきか、判断がつかないまま作成に踏み切れない方が多いのも実情です。
2.遺言書の主な種類
一口に「遺言書」といっても、大きく以下の3種類に分けられます。それぞれ作成の手順や保管方法、証人の有無などに違いがあります。
2-1.自筆証書遺言
自分で紙とペンを用意して、全文を自筆で書く形式の遺言書です。費用がほとんどかからず、手軽に作成できるという点が特徴です。ただし、自分で書く以上は法律上の書式を守り、遺言書としての要件を十分に満たす必要があります。
2-2.公正証書遺言
各都道府県の公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公証人が関与して作成する、かつ遺言書の原本が公正証書として公証役場に保管されるため、形式不備や紛失リスクが少ないという大きなメリットがあります。
2-3.秘密証書遺言
自筆証書遺言と同様、遺言書自体は自分で作成しますが、その内容を第三者に見せなくてよい形式です。ご自身で遺言書を作成のうえで封をした状態にし、証人の立会いのもとで公証人に「秘密証書遺言」として存在を証明してもらいます。内容は公開したくないが、公的な形式を整えたいという方が選ぶケースが多いです。
2-4.併せて知っておきたい法務局保管制度
自筆証書遺言の場合は「法務局での保管制度」を利用することができます。これは、法務局に自筆証書遺言を持ち込み、正式に保管してもらう制度で、紛失・改ざんリスクを大きく減らすことが可能です。また、保管された遺言書は家庭裁判所の検認手続が不要となるため、後々の手続がスムーズになるメリットもあります。
3.それぞれの遺言書のメリット・デメリット
ここでは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言それぞれの特徴を比較しつつ、メリット・デメリットをもう少し詳しく解説します。
3-1.自筆証書遺言
メリット
☑ 費用がほとんどかからない(基本的には紙とペンだけで作成可)
☑ 自分の都合の良いときに作成・変更ができる
☑ 内容を完全に秘密にできる(保管方法を工夫すれば第三者に見られにくい)
デメリット
☑ 法的要件を満たさない場合は遺言自体が無効となるリスクがある
☑ 紛失や改ざんの可能性がある
☑ 全て直筆で書く必要がある
☑ 死後に検認手続が必要で、相続人に負担がかかる
3-2.公正証書遺言
メリット
☑ 公証人が作成するため形式不備の心配がほぼない
☑ 原本が公証役場に保管されるので紛失のリスクがない
☑ 検認手続が不要
デメリット
☑ 作成時の手数料や証人手数料など、ある程度の費用がかかる
☑ 公証役場まで出向く必要があり、証人も2名以上必要
☑ 遺言内容を証人や公証人が知るため、完全秘密にはできない
3-3.秘密証書遺言
メリット
☑ 署名以外は直筆でなくても作成が可能
☑ 内容自体は封印されたままなので、証人や公証人にも知られずに済む
☑ 公的な手続きで遺言書の存在を証明できるが、作成コストが公正証書遺言に比べて低い
デメリット
☑ 公正証書遺言ほどの安全性はなく、形式不備のリスクが残る
☑ 検認手続が必要
☑ あまり利用する人が少ないため、実務的なノウハウが少ない場合もある
4.遺言書の種類による費用や手間の違い
遺言書の種類によって、かかる費用や手間は大きく異なります。たとえば、自筆証書遺言なら用紙や筆記用具程度しか費用がかかりませんが、法的要件を満たしているかを法律の専門家に相談しないままだと、不備があったときに想定外のトラブルにつながりかねません。また、公正証書遺言の場合は公証人役場での手数料が発生しますが、その分形式的な安心感は大きく、紛失のリスクも大幅に減らせます。
ご自身の財産規模が大きい方や、相続人が多数いて意見の衝突が想定される方は、その後の遺言執行まで見据えて公正証書遺言を選ぶケースが多いです。一方で、財産がさほど多くなく、まずは費用を抑えて作成したいという方は自筆証書遺言を選ぶ場合もあります。ただし、その場合でも「法務局保管制度」を利用すれば安全性を高められるため、最近は利用する方が増えてきています。
5.自分に合った遺言書を選ぶポイント
遺言書の種類を選ぶ際は、以下のポイントを総合的に検討することをおすすめします。
5-1.財産規模・内容
財産の総額や種類が多岐にわたる場合、公正証書遺言にしておくと形式不備による無効リスクを最小限にできるため安心です。たとえば土地や不動産が複数ある、株式や投資信託などの金融資産が多い、といった場合は特に注意が必要です。自筆証書遺言にする場合でも、弁護士に事前に確認してもらうことで、書式や分配方法に不備がないかどうかをチェックできます。
5-2.相続人間の関係性
相続人が複数いてその関係が複雑な場合は、遺言書の「正当性」や「信頼性」が極めて重要になります。あとから「こんな遺言書は無効だ」と言われないように、公正証書遺言を選んでおくほうが望ましいケースが多いです。一方、相続人が限られていて、特に紛争が起こる可能性が低い場合は、自筆証書遺言でも問題なく運用できる場合があります。
5-3.直筆で全文を書けるかどうか
自筆証書遺言は全文を直筆する必要があるため、長文の筆記が困難な方には大きな負担です。一方、公正証書遺言なら公証人が作成を補助してくれるほか、秘密証書遺言であれば署名以外はパソコンでの作成でも可能なため、直筆でなくても遺言書の作成ができます。ご自身の身体状況や負担を踏まえ、無理のない形式を選択しましょう。
5-4.遺言書を書き直す頻度
相続人の増加、財産の変動などに応じて遺言書の内容を頻繁に書き直したいと思っている場合は、その都度手数料がかからない自筆証書遺言の方が適しています。一方、あまり変更予定がない方は、公正証書遺言の安全性と信頼性を優先するほうが安心です。将来の改定頻度や費用対効果を踏まえ、最適な形式を選んでみてください。
6.相続LOUNGEのワンストップサポートの強み
遺言書の作成を含む相続対策では、法的な視点だけでなく、税金や不動産登記など幅広い専門知識が求められます。そこで、相続LOUNGEでは、弁護士・税理士・司法書士が連携し、ワンストップでサービスを提供しています。
6-1.弁護士・税理士・司法書士の一貫したサポート
弁護士
主に相続紛争の予防・解決から遺言執行、相続手続などを担当します。万が一、遺産分割協議がもつれて調停や訴訟に進んだ場合でも、速やかに対応可能です。
税理士
主に相続税申告や贈与税申告、財産評価、事業承継対策など、税務面のサポートを担当します。将来発生する二次相続や節税を見据えた分配案の立案にも貢献します。
司法書士
主に不動産の相続登記手続を担当します。弁護士と共同の上で、相続人調査や遺産調査といった事前段階から、名義変更まで一貫してフォローが可能です。
通常は各専門家との相談が必要になりますが、相続LOUNGEではこれら複数の士業が一体となって動くことで、お客様が別々に専門家を探す手間を省き、コミュニケーションロスも大幅に減らすことができます。
6-2.将来の紛争防止と節税対策
遺言書は一度作成して終わりではなく、その後のライフプランや財産状況の変化に合わせて見直しが必要です。当事務所グループなら、弁護士が遺産分割による紛争を防止する内容で遺言書内容を検討し、税理士が相続税の節税対策を提案し、司法書士が必要に応じて名義変更登記を行うといったトータルサポートが可能です。
6-3.遺言執行や信託など幅広いサービス
遺言執行業務
遺言書の内容を実現するための手続一式を遺言執行者として対応いたします。相続人間で意見が合わないときも、法律専門家として公正に執行を進めます。
死後事務委任
葬儀や遺品整理など、ご本人が亡くなった後に必要となる手続を生前に契約で定めておき手続きを行います。遠方に住むご親族が負担を抱えなくて済むよう配慮できます。
信託
自身の財産管理を第三者に任せる「家族信託」など、柔軟な資産承継プランの構築が可能です。
相続LOUNGEでは遺言書作成のほかにも「遺言執行業務」「死後事務委任」「任意後見契約」など、作成した遺言書の確実な履行手続や将来の財産管理や身の回りの手続にも対応しています。
こうした幅広い業務を一貫して行えることは、弁護士・税理士・司法書士が連携を行う相続LOUNGEならではの大きな強みです。
8.本コラムのまとめ:遺言書の作成についてお悩みの方は、まずは無料相談へ
遺言書の種類は、大きく「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分かれ、それぞれ作成費用や手間、紛失リスクや検認手続の必要性などが異なります。どれを選ぶかは財産規模や相続人間の関係性、将来の紛争リスクや税務対策を総合的に考慮して判断すべきです。
相続LOUNGEでは、弁護士だけでなく税理士・司法書士が在籍しており、遺言書作成から遺言執行、相続税申告や名義変更までワンストップで対応しています。自筆証書遺言の場合の法務局保管制度の活用や、公正証書遺言を選ぶ際の手続きの流れ、節税につながる遺産分割の工夫など、専門家ならではの視点を活かしたサポートが可能です。
遺言書を作成することで、ご自身の想いを確実に反映し、大切なご家族に余計な負担をかけずに済むようになります。将来の安心を得るためにも、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。