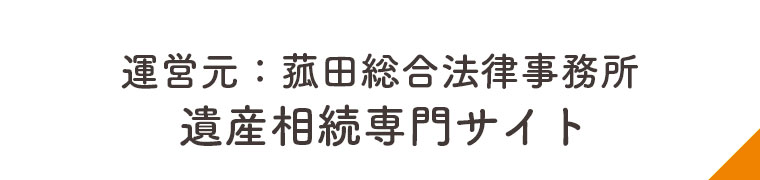遺言書の正しい保管方法
- HOME
- お悩み別コラム
- 遺言書を作成したい・遺言執行者を選任したい
- 遺言書の正しい保管方法
動画でわかりやすく解説!
遺言書をどのような方法で保管しておくかは、生前の意思を遺されたご家族や身近な人達に正確に伝える上で、非常に大切です。
今回は、遺言書の保管にはどのような方法が存在するのかをご説明したいと思います。
1.自筆証書遺言の保管方法
自筆証書遺言の保管方法は、主に以下の2つの方法があります。
(1)自己保管
自筆証書遺言の保管方法で、最も一般的なのが自己保管です。その際の保管場所は自宅の金庫や仏壇などに置かれる方が多いです。
(2)第三者に預ける
自己保管だと、家族に見られたりする心配があるため、第三者に預ける場合もあります。ここでいう第三者とは、以下のような場合が考えられます。
〇親族等
親族に遺言書を預けるということは、法律上問題はありませんが、遺産の利害関係にある親族へ預けることは、あまりおすすめできません。
利害関係にある親戚に預けた場合、(1)自己保管 のときと同じように、遺言書の隠匿や書き換えが起こり、親族間のトラブルになりかねないからです。
第三者に預ける際は、利害関係のない第三者に預けるようにしましょう。
〇専門家事務所に預ける
専門家事務所とは司法書士や税理士、弁護士などです。これらの専門家事務所は、遺言書の保管だけではなく、作成方法を教えてくれたり、遺言執行者を引き受けたりもしてくれるため、遺言書に関することをすべてお任せすることが出来ます。
また、これらの専門家には守秘義務が課せられているため、遺言書の内容を第三者に知られてしまう心配もありませんので、自筆証書遺言の保管方法としては、専門家事務所に預ける方法が一番おすすめです。
以上が、自筆証書遺言の主な保管方法になります。
次は、公正証書遺言の保管方法についてご説明したいと思います。
2.公正証書遺言の保管方法
公正証書遺言を作成した場合は、作成した公証役場で遺言書の原本が保管されることになっています。遺言者の死後、相続人やその代理人(弁護士など)が公証役場に問い合わせることで遺言書の有無を確認することができます。
ですので、遺言書を作成したという事実と、保管場所の公証役場を事前に相続人へ伝えておくことで、相続開始時にすみやかに遺言書を確認してもらうことができます。
中には、自分が書いた遺言書について相続人に話してしまうことでトラブルになったりしないのか?と心配される方もいるかもしれません。
しかし、公正証書遺言の場合は遺言書の存在が知られてしまっても、相続人が自由に中身を見ることは出来ず、書き換えられてしまう心配はないので、伝えてしまっても問題はありません。
加えて、公正証書遺言の場合は、裁判所での検認手続きが不要です。自筆証書遺言の場合は開封する前に検認を受けなければ遺言自体が無効になってしまう可能性もありますが、公正証書遺言はその心配もなく、検認手続きにかかる相続人の手間も省くことができます。
3.2020年から実施!新しい保管方法
現段階では、遺言書の保管方法は前述した方法が主な方法ですが、実は、民法改正に伴い、2020年7月10日から新たな保管方法が実施されることになります。
新しい保管方法は、これまで自己保管や第三者に預けるしか方法がなかった自筆証書遺言を、法務局で保管することが可能になります。それにより、自筆証書遺言保管の際の懸念点が大幅に解消されることになりました。
この、法務局での保管方法について3つのポイントを詳しくご説明したいと思います。
①保管申請
まず、法務局での自筆証書遺言の保管の手続きは、
遺言書を書く人の住所地、本籍地、所有している不動産の所在地 を管轄している法務局で行うので、該当の法務局に保管の申請を行います。
この時の申請は、遺言者本人が自ら出向いて行う必要があります。また、本人確認のために本人確認書類の持参が必要になります。
さらに、申請の際に遺言書の中身の確認が行われるため、封をしていない状態で持っていく必要があります。
一連の保管申請手続きが終われば遺言書は適切に法務局内で保管されます。
②遺言書の訂正が可能
法務局で自筆証書遺言を保管する際は、公正証書遺言書よりも容易に内容の訂正を行うことが可能です。
公証役場で公正証書遺言を保管した場合は、内容を少しだけ訂正したいという場合も一から作成するときと同じように、書類の準備や証人の立ち会いが必要になります。(公正証書遺言の詳しい作成方法は「公正証書遺言ってなに?」https://www.legal-kyushu.jp/inheritance/will-by-notarized-document/ を参照ください。)
一方、法務局で自筆証書遺言を保管している場合は、自筆証書遺言の訂正なので、該当箇所のみ訂正を行えばよく、手間が少なくて済みます。
③相続開始後の手続き
法務局での遺言書保管を行ったときは、相続開始後(遺言者の死後)以下のような特徴があります。
・検認が不要
相続開始後、自筆証書遺言はすぐに封を開けてはならず、家庭裁判所に持っていき検認作業をしてもらう必要がありますが、法務局で保管をしている場合は、申請時に内容の確認が行われているため、この検認作業が不要になります。
「間違って検認前に遺言書を開封してしまい、遺言が無効になってしまった」という事態を防ぐことが可能になるのです。
・自分が相続人となっている遺言書が保管されているかどうかの確認が可能
遺言者の死後、全国の法務局内にて、自分が相続人・受遺者になっている遺言書が保管されているかどうかを確認することが可能です。これは、法定相続人でなくても、誰でも確認することができます。
・遺言書原本・画像データの閲覧(相続人や受遺者のみ)
遺言書原本の閲覧は、遺言書が保管されている法務局でしかできませんが、画像データの閲覧は全国各地の法務局にて閲覧可能です。
なお、これらは遺言書で相続人・受遺者となっている人のみが閲覧することが出来ます。
以上の特徴を見て頂くと、法務局での保管が可能になれば、自筆証書遺言の「隠匿・書き換えの恐れ」や「遺言書の存在が不明」という懸念点が解消されることになります。
公正証書遺言よりも手軽に作成が可能で、公正証書遺言同様に安心・安全に保管されてなおかつ発見されやすい遺言書が実現されるので、法務局での遺言書の保管が主流になる可能性が高いです。
<それぞれの保管方法の特徴>
| 自己保管 | 親族 | 専門家事務所 | 公正役場 | 法務局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | かからない | かからない | かかる | かかる | かかる |
| 遺言書の訂正 | 好きなときにできる | 好きなときにできる | 事務所に出向き、修正可能 | 再度作成しなおさなければならない | 法務局に行けばいつでも訂正が可能 |
| 発見されやすさ | 自宅にあるので比較的発見されやすい | 預かっていた親族により遺言書の存在が伝えられる | 保管場所を生前に伝えておけば発見される | 保管場所を生前に伝えておけば発見される | 全国の法務局で遺言書の有無が確認可能なため発見されやすい |
| 保管の安全性 | 紛失・相続人による隠匿・書き換えの恐れがある | 親族による隠匿・書き換えの恐れがある | 守秘義務に基づき適切に管理される | 紛失や第三者の手に渡る恐れがない | 紛失や第三者の手に渡る恐れがない |
| 検認の有無 | 検認手続きが必要 | 検認手続きが必要 | 検認手続きが必要 | 検認手続きが不要 | 検認手続きが不要 |
4.遺言書の保管と災害対策
自然災害によるリスク
地震や台風、大規模火災などが多発する昨今、自宅で保管していた遺言書が消失してしまうといったリスクも懸念しておかなければなりません。せっかく作成した遺言書が災害で失われてしまえば、遺されたご家族が本来の遺志を正しく受け継げないまま、相続手続を進めなければならない状況になりかねません。防災対策の一環として、遺言書の保管方法を今一度見直すことが大切です。
遺言書の消失を防ぐには?
まずは、自宅保管よりも消失しにくい場所での保管に切り替えるというのがリスクを減らす方法の一つです。代表的なものとしては、金融機関の貸金庫が挙げられます。月額や年額で利用料がかかるものの、防犯や耐災性に優れており、貴重品や重要書類の保管に適しています。また、法務局保管制度を利用すれば、自筆証書遺言の原本を公的に預けられるので、災害時でもリスクを大幅に下げることが可能です。
どうしても自宅で保管をしておきたいという場合は、例えば非常用の持ち出し袋の中に遺言書を入れておくなど、何かあったときにすぐに持ち出せるように準備をしておくとよいでしょう。
最近は書類をスキャンしてクラウドに保存する方法も注目されていますが、現行法では遺言書のデータ化そのものに法的効力はなく、「紙の原本」が必要になります。紙媒体の遺言書をどのように守るかを念頭に置いて、保管環境の整備が必要です。
5.相続人に内緒で書いた遺言書をどう保管するか
生前は秘密に、死後は発見してほしいというジレンマ
相続人同士の対立が予想される場合、遺言書はきちんと準備はしているものの、その存在を生前に知らせたくないとおっしゃられる方も一定数いらっしゃいます。見つけやすさを考えると自宅に置いておきたい、でも中身は見られたくないし、紛失・改ざんは避けたいというように、「内容を秘密に」と「死後には確実に見つけてもらう」というところを両立させるには保管方法の工夫が必要です。
秘密証書遺言と貸金庫保管の組み合わせ
まず、遺言の内容を他人に知られたくないなら、秘密証書遺言がひとつの選択肢です。封印した遺言書を公証人と証人に示すことで、遺言自体の存在証明を確保しつつ中身を秘匿できます。ただし、秘密証書遺言の場合は公証役場での保管は行っていないため、実際の保管場所が不明だと発見されないままになる恐れがあります。
そこで、例えば金融機関の貸金庫に保管をし、相続人には貸金庫がある旨だけを伝えておく(遺言書があることは明言しない)ことで、災害や盗難から保護しつつ、相続が開始されたタイミングで相続人に遺言書を発見してもらえる可能性が高まります。
保管と周知のバランスを考える
「絶対に知られたくない」という思いが強いほど、遺言書が発見されにくくなるのも事実です。最終的に遺言書が見つからないという事態は避けるべきですので、どうしてもという場合は信頼できる第三者や専門家にだけ保管場所を伝えておく、あるいは保管自体は貸金庫等で行い必要最低限の情報だけを共有するなど、秘密を保持しながらも死後には確実に見つけてもらう――このバランスをどう取るかが、大きなカギとなるでしょう。
6.本コラムのまとめ
遺言書の保管方法には、それぞれメリット・デメリットが存在していましたが、2020年の民法改正により、デメリットが解消された新たな保管方法が実施されることになりました。それにより、遺言者の最後の意思の実現や相続手続きの円滑化が可能になり、遺言書の主流な保管方法が取って代わる日も近いかもしれません。
なお、遺言書の保管方法は、遺言書の作成の仕方によって選択肢が異なります。
ご自身の希望する保管方法が実現できる方法で遺言書を作成する必要がありますので、ご不安な場合は作成をされる前に一度専門家へご相談ください。