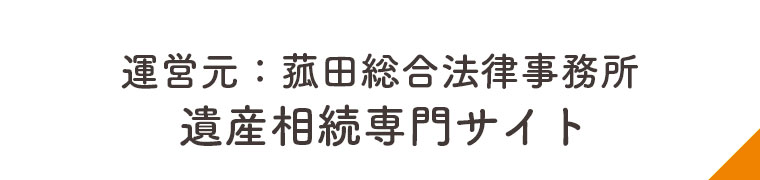弁護士が解説する「遺言執行者の選任」とは?選ぶメリット・手続きのポイント
- HOME
- お悩み別コラム
- 遺言書を作成したい・遺言執行者を選任したい
- 弁護士が解説する「遺言執行者の選任」とは?選ぶメリット・手続きのポイント
動画でわかりやすく解説!
「遺言書を書いたものの、遺言執行者は本当に必要なのだろうか」「遺言執行者を誰にすればいいか、選任の基準がよくわからない」──遺言書に関心を持つ方の多くは、このような疑問を抱えていらっしゃいます。実際、遺言書をどれほど丁寧に作成しても、遺言執行者をきちんと選任していないがために、遺言の内容が正しく実現されないケースは少なくありません。
本記事では、専門家の立場から「遺言執行者の選任」について詳しく解説いたします。まずは遺言執行者の役割や権限をわかりやすく整理し、選任するメリットや具体的な手順をお伝えします。
1.遺言執行とは?
遺言者が亡くなったとき、遺言書の内容を実現させるため、遺言書の内容に沿って遺産相続手続きが行われます。これを遺言執行と言います。また、遺言執行に必要な手続きをまとめて行う人のことを、遺言執行者と言います。
遺産相続なら、相続人たちで力を合わせて手続きを行えば出来るので、わざわざ遺言執行者は必要ないのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、相続人同士の協力があれば、相続手続きを完了させることはできますが、中には相続人同士で揉めてしまう相続があったり、相続人同士が遠方に住んでいたりで、なかなか手続きが円滑に進められない場合があります。そういったときに遺言執行者がいれば、揃える書類なども少なく、最低限の手間と時間で遺産相続を進めることが可能になるのです。
遺言執行者とは何か?
遺言執行者とは、遺言者が残した遺言書の内容を実際に実現する役割を担う存在です。法律上は、遺言書に書かれた指示を執行する「代理人」のような立ち位置にあり、相続が始まった後に財産の名義変更や遺贈の実行、相続人への連絡など、遺言内容を具体的な形にするための手続を行います。
遺言書は、あくまで「遺言者の意思を記した文書」にすぎません。そこに書かれた内容が円滑に履行されるためには、相続発生後に誰かが具体的な手続きを進める必要があります。だからこそ、遺言執行者の役割は非常に重要です。もし遺言執行者を明確にしていないと、相続人同士で手続の進め方に意見が割れたり、結果として遺言書が形骸化してしまったりするリスクもあります。
遺言執行者になるには、特別な資格が必要なわけではなく、未成年者や破産者など例外を除けば誰でもなることができます。
しかし、相続人の1人が遺言執行者になってしまうと、財産の分配(2. 遺言執行者の役割 で後述します)を行ったりするため他の相続人から、「財産の独占をしているのではないか」などあらぬ疑いを掛けられてしまい、相続人同士のトラブルになりかねません。
そういったトラブルを防ぐため、また手続きも専門的で複雑なこともあるので、遺言執行者は相続手続きに詳しい専門家を選任するのがおすすめです。
次に、遺言執行者の必要性がより分かるように、具体的な遺言執行者の役割についてご説明したいと思います。
-
2.遺言執行者の役割
遺言執行者の役割(=権限)は、大きく以下の6つに分けられます。
-
①財産目録の作成
まず、相続が発生したら、財産を証明する書類(登記簿や権利書等)を揃えて財産目録を作成し、相続人に提示します。
②相続人の相続割合の指定・分配
実行する遺言の内容に沿って、各相続人の相続割合と遺産分配の指定を行い、実際に遺産の分配を行います。このとき、登記申請や、金銭取り立て(不動産が相続遺産である場合の賃料の取り立て)も遺言執行者が行うことができます。
③相続財産の不法占有者に対して明渡・移転の請求をする
相続遺産の土地や建物等を不法に占有している者がいる場合は、明渡や移転の請求をすることが出来ます。
④相続人以外への遺産の引渡
遺言書に、相続人以外へ遺産を遺贈したいと記載されている場合は、その通りに遺産の引渡を行います。
⑤戸籍の届出
遺言者が遺言書によって子どもを認知※した場合は、戸籍の届出を行います。
※認知:結婚していない男女間に生まれた子供は、父親が認めることにより父と子の関係が法的に認められます。この行為を認知と言い、遺言で認知をし、戸籍の届出を行うと、相続人が増えるということになります。
⑥相続人の廃除・廃除の取消
遺言者は、相続人に遺産を相続させたくない場合、生前に家庭裁判所で手続きを取るか、遺言書に記載しておくことで相続人を廃除することが可能です。しかし、遺言書に書いただけでは実際には廃除することはできないため、代わって遺言執行者が家庭裁判所で手続きを行い、相続人の廃除を行うことが可能となります。
反対に、一度生前に相続人の廃除を行ってしまって、撤回したい場合は遺言書で廃除の取消を行うことが可能で、遺言執行者によって手続きが取られます。
これらが、遺言執行者が行う役割になります。このように見てみると、遺言書を書いておくことで死後出来ることもいろいろと存在しているのだな、ということが分かりますね。
次は、遺言執行者は実際に選任しておくべきかどうかについてお話しておきたいと思います。
-
3.遺言執行者を選任すべき理由
遺言執行者は、遺言書を書くからといって、必ずしも選任しなければいけないわけではありません。しかし、選任しておくべきメリットは非常に大きいので、選任しておくことをおすすめします。遺言執行者を選任しておくべき理由は、「相続手続きがスムーズに進めることができ、遺された家族に面倒な思いをさせないで済むから」というのが大きいでしょう。
具体的に、遺言執行者を選任している場合と、していない場合でどれくらい手続きの内容が違ってくるのでしょうか?
以下、銀行手続きの一例を用いて遺言書で遺言執行者を選任している場合と、していない場合の必要書類を比較した表になります。
| 相続手続き(銀行手続き)に必要な書類 (遺言書通りに相続する場合) |
|
|---|---|
| 遺言書で遺言執行者を選任している場合 | 遺言執行者を選任していない場合 |
| ・遺言者の戸籍謄本 ・遺言執行者の印鑑証明書 ・遺言執行者の実印 ・遺言書(原本) ・検認済証明書(自筆証書遺言の場合) ・遺言者の通帳・証書・キャッシュカード等 その他、各銀行での必要書類がある場合あり |
・遺言者の戸籍謄本 ・遺産を相続する人全員の印鑑登録証明書 ・遺産を相続する人全員の戸籍抄本(または謄本) ・手続を行う受遺者の実印 ・遺言書原本または公正証書遺言(正本か謄本) ・遺言者の通帳・証書キャッシュカード等 その他、各銀行での必要書類がある場合あり |
こちらの表を見て頂くと、遺言執行者を遺言書で選任している場合は、銀行手続きの際に、わざわざ相続人に関する書類を集める必要がないことが分かります。一方、遺言執行者を選任していない場合は、遺産を相続する人全員の印鑑登録証明書や戸籍が必要となります。
この場合、何が問題かというと、印鑑証明を取りに行く、という手間も生じますし、万が一、遺言書に書いてある遺産分割方法に納得がいっていない人がいる場合、印鑑証明書を取得してもらえず、手続きが進められないという可能性があります。その場合は、遺産分割協議を行い全員が納得できる形での遺産分割を進めることとなりますが、こうなってしまうと遺言書通りの遺産分割方法にならず、遺言者の意思に沿わない結果となることも考えられます。
その点においても、遺言執行者を選任しておくと、遺言書の内容通りに相続をスムーズに進められるということが言えます。
遺言執行者が事実上必須と言えるケース
前述したとおり、遺言執行者の選任は、法律で義務付けられているわけではありません。ただし、遺言の内容や状況によっては、選任がほぼ必須と言えるケースも存在します。たとえば、「認知や推定相続人の廃除を行う条項を含む遺言書」などは、法的にも遺言執行者がいないと実行が難しくなるため、事実上執行者の選任が必要となります。
なお、法的には遺言執行者は必須ではありませんが、遺言執行者をきちんと定めておくことが、遺言の実効性を高めるためのカギとなりますので、「自分の遺言内容が本当に実行されるか不安」という方は、積極的に選任を検討することをおすすめします。
4.誰を遺言執行者に選任すべきか
法律上、未成年者や破産者などを除き、基本的にはどなたでも遺言執行者として選任可能です。ただし、遺言執行は法的な知識が一定程度必要になるため適切な人選をする必要があります。以下では、代表的な候補者とそのメリット・デメリットを見てみましょう。
親族を遺言執行者に選任する場合
【メリット】
■財産内容や家族事情をよく理解している
■相続人同士のコミュニケーションが比較的スムーズ
■報酬負担が比較的少ない
【デメリット】
■感情的な対立が起きると、中立性を保ちにくい
■相続人間で「えこひいきがあるのでは?」と疑念を持たれがち
■法的手続の面で、手続が長期化する可能性がある
弁護士などの専門家を遺言執行者に選任する場合
【メリット】
■法律知識が豊富で、複雑な相続手続にも対応可能
■税理士や司法書士と連携できる専門家であれば、一括して手続を進められる
■公平中立な立場でスムーズに執行し、相続人間の紛争を防ぎやすい
【デメリット】
■一定の報酬が必要になる
■相続財産の規模が小さい場合、費用対効果を考慮する必要がある
複数人の遺言執行者を選ぶことは可能か
遺言執行者は一人でなければならないわけではなく、複数人を同時に指名することもできます。ただし、複数の執行者がいる場合は、お互いの権限や役割分担を明確化しておかないと、かえって手続が混乱する恐れがあります。特に、不動産の名義変更や金融機関での対応などは、権限が重複すると実務が停滞するケースもあるため注意が必要です。
5.遺言執行とは?
遺言執行者の選任には、大きく分けて「遺言書を通じた方法」と「家庭裁判所への申立て」の2種類があります。以下では、具体的な手順と流れを解説します。
遺言書における指定
最も簡単な方法は、遺言書に直接「遺言執行者を〇〇に指定する」と記載しておくパターンです。あるいは、「遺言執行者の指定を弁護士〇〇に委託する」と定めておく方法もあります。いずれの場合も、相続開始後にその人が自動的に遺言執行者となるため、別途の選任手続は必要ありません。
家庭裁判所への選任申立
遺言書に執行者の指定がない、または指定されていた人物が辞退したなどの理由で空席となった場合は、相続人など利害関係人が家庭裁判所に「遺言執行者選任」の申立てを行うことが可能です。申立を行う際に遺言執行者として指定するのは専門家以外の人間でも問題ありませんが、遺言執行の内容によっては遺言執行者を専門家にしてくださいという判断が出る場合もありますので、その場合は弁護士等の専門家を遺言執行者にする必要があります。
6.遺言執行者の“辞任・解任”と対処法
遺言執行者は、故人の最後の意思を具体的な手続に反映させる重要な役割を担いますが、実務では「執行者本人が辞任したい」「相続人が執行者の解任を求める」という事態が起こることもあります。
遺言執行者の辞任が認められる事例・認められない事例
そもそも、遺言執行者は被相続人の遺言書によって指名された存在であり、相続開始後は法的な義務を負う立場です。しかしながら、やむを得ない事情がある場合などは、辞任が認められることがあります。たとえば、以下のような状況が考えられます。
【健康上の理由】
高齢や病気などで業務を継続することが困難になった場合、辞任を申し出ることで実質的に手続を進められない状態を回避するほうが合理的だと判断されることがあります。
【相続人との深刻な対立】
親族間の対立が激化し、執行者としての中立的立場が保てなくなった場合も、辞任を選択せざるを得ないケースがあります。
一方で、単なる「忙しくなったから」「報酬が思ったより少ないから」という程度の理由では、直ちに辞任が認められにくいといえます。遺言執行者には、その地位を一方的に投げ出さず、誠実に業務を遂行する責任があるからです。もし辞任を希望する場合は正当な手続を踏むことが大切です。
遺言執行者の解任を求めたい場合
遺言執行者が不適切な行動をしたり、職務を全く果たしていない場合には、相続人の側から「解任」手続きを求めることができます。具体的には、家庭裁判所に対して解任の申立てを行い、下記のような点を主張・立証する流れです。
【不正行為や重大な義務違反の存在】
財産の横領や管理上の大きなミス、相続人への説明義務違反などが典型的な理由となります。
【執行者としての適格性を欠いていること】
判断能力に問題がある、あるいは故意に手続を放置しているなど、執行者に相応しくない事情がある場合です。
解任の可否は、家庭裁判所が「遺言執行者としての職務を継続させるのが相当かどうか」を総合的に判断して下します。解任が認められた場合は、新たな執行者を選任するための手続を並行して進める必要があり、相続人にとっても手間と時間がかかるのが実情です。
新たな遺言執行者を選び直す際の注意点
仮に辞任や解任によって執行者の席が空いてしまったら、相続人などの利害関係人は改めて新たな執行者を選任しなければなりません。遺言書で「第二候補者」や「執行者の指定を別の専門家に委託する」といった規定があれば、その手続に従うのが基本です。もし遺言書に何も定めがなければ、家庭裁判所に選任申立を行って、正式に新執行者を確保します。
新たな執行者を決める際には、以下の点を考慮しておくと、二度手間や再トラブルを防ぎやすくなります。
【執行の途中経過をしっかり把握する】
辞任・解任時点までにどのくらい手続が進んでいるかを確認し、財産目録や登記書類、銀行手続の状況などを漏れなく引き継ぐ必要があります。
【専門家の選任を検討する】
再度トラブルが起きないよう、公平中立な弁護士や司法書士に依頼するのも一つの手段です。相続人同士の対立が激しい場合は、第三者的立場の専門家を執行者にする方が紛争予防に効果的です。
【相続人間の意見調整を丁寧に行う】
執行者が代わったことに対する疑念や不信感が募らないよう、こまめな情報共有や協議の場を設けることが大切です。
辞任・解任のようなイレギュラー事態が起きると、相続手続全体が遅れたり余計な費用が生じたりするため、できるだけ避けたいところです。とはいえ、やむを得ない事情があるなら、適切な法的手続を通じて解決するしかありません。遺言執行者を辞退したい、またはすでに選任されている遺言執行者に思うところがある場合は、一度専門家に相談の上で辞任・解任の手続を進めることも一つの手です。
7.まとめ
遺言書は、被相続人の想いを法的に実現するための重要な手段ですが、実際にその内容を執行しなければ意味がありません。そこでカギを握るのが「遺言執行者の選任」です。専門家を遺言執行者として選任すれば、相続税や不動産登記など多方面にわたる専門知識を活かし、迅速かつ的確に遺言を実現できるでしょう。
相続LOUNGEを運営している「Nexill&Partners Group」は、グループ内に弁護士法人・税理士法人・司法書士法人を擁しており、相続に関する幅広い業務をワンストップで対応できます。遺言執行者として弁護士が就任し、そのバックアップとして税理士が相続税申告を行い、司法書士が相続登記を行う──このような連携体制が整っているため、煩雑なやり取りを最小限に抑えつつ、専門性の高いサービスを提供できるのが強みです。
「自分の遺言書は本当に実行されるのか」「相続人が多く、紛争の心配がある」など、少しでも不安をお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。