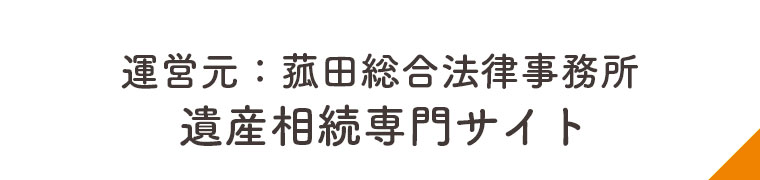養子縁組で戸籍はどうなる? | 基礎知識と戸籍の注意点を弁護士が解説
「養子縁組をすると戸籍上の扱いはどうなるのか」「実親との法律関係はどう変わるのか」──こうした疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。相続の場面では、養子縁組により法定相続人の範囲や相続分が変わる場合もあります。そこで本記事では、養子縁組と戸籍の基本的な関係を解説したうえで、相続における影響や注意点を弁護士の視点から整理します。さらに、相続LOUNGEが提供するワンストップサービスのメリットにも触れながら、円滑な相続を実現するためのヒントをお届けします。
1.養子縁組の基本──どんな種類があるのか
養子縁組とは、実親子関係ではない者同士が、法律上の親子関係を発生させる制度です。民法上、大きく普通養子縁組と特別養子縁組の2種類が存在します。
普通養子縁組
養親と養子の双方が合意して締結するもので、基本的に実親との親子関係は法律上残るのが特徴です(親が増えるイメージ)。
特別養子縁組
子の福祉の観点から、実親との法律上の親子関係を終了させて、養親との関係に一本化する制度です。特に未成年者(15歳未満)を養う場合に活用されることが多く、家庭裁判所の許可が必須です。
いずれの縁組も、相続の場面では「養子が相続人となるかどうか」に影響を及ぼし得ます。ただし、特別養子縁組では実親との法律関係がほぼ失われる(相続関係が断たれる)一方、普通養子縁組では実親の相続人としての地位が維持されるなど、どの方式を選ぶかによって相続の形が変わる点に注意が必要です。
2.養子縁組で戸籍はどうなる?
2-1.養子縁組後の戸籍上の取り扱い
普通養子縁組の場合、養子となる人は養親の戸籍に入るのが一般的です。戸籍謄本を取り寄せると、養子としての記載が追加されることになります。一方、特別養子縁組の場合は、より実子に近い扱いを受けるため、戸籍において実親との関係が閉じられ、養親の戸籍に入るという形です。 なお、戸籍上の氏名をどうするか(改姓をするかどうか)も、法律上の取り扱いが変わるポイントです。たとえば、養子となる者がすでに成人していても、原則として養親の氏に変更されるため、どの時点で戸籍を移すかのスケジュール感が重要になります。
2-2.実親との法律関係
普通養子縁組では、戸籍が養親のほうに移ったとしても、実親との相続関係が残ります。つまり、養子は実親からも相続できる可能性があるわけです。一方、特別養子縁組では実親との親子関係が法律上終了するため、実親の相続については原則として関係がなくなる点に注意を要します。 この違いは、将来の財産承継や家庭内の法的整理に大きく影響を及ぼすため、養子縁組を検討する場合には事前に弁護士や専門家に相談し、戸籍上の取り扱いと相続への影響をしっかりと踏まえておくことが望ましいでしょう。
3.相続に及ぼす影響──養子縁組で相続人は変わる?
3-1.「普通養子」と「特別養子」での違い
養子縁組を行った場合、養子は法定相続人としての地位を得ますが、普通養子縁組と特別養子縁組では、実親との関係がどうなるかが異なるため、相続の範囲も異なってきます。
普通養子:養親の相続人になると同時に、実親の相続人としても資格を失いません(ただし、一部例外もあります)。
特別養子:養親の相続人にはなりますが、実親との法律上の親子関係がほぼ消滅するため、実親の相続に関しては原則として相続権が及ばなくなります。
3-2.養子縁組が有効かどうか争点になるケース
相続において問題となるのは、「そもそも養子縁組が有効に成立していたかどうか」という論点です。 たとえば、高齢者が自身の介護者を養子に迎えた場合に、ほかの相続人から「意識が不十分な状態で署名したのでは」「事実上の強制だったのでは」などと主張され、縁組の無効・取り消しを求める裁判に発展するケースもあります。結果として、養子に相続権が発生するかどうか、根本的に争われることがあるのです。 このように、相続の際には戸籍の取り寄せを行い、確実に縁組が存在したのか、成立要件は満たされているのかをチェックすることが重要です。
4.養子縁組の際に気を付けたい戸籍手続き
養子縁組を行うと、戸籍の筆頭者が変わる、あるいは新しい戸籍がつくられる場合があります。たとえば、妻側の氏を選択している夫婦が養子を迎えるときなど、どのタイミングで戸籍を動かすか慎重な判断が必要です。 また、成人している子どもを養子とする場合には、改姓の手続きや住民票の変更など、戸籍のほかにも関連手続きが発生します。これらを怠ると、実生活や相続時の手続きに不都合が生じる恐れがあります。
5.養子縁組が無効となる場合も?──法的リスクと対策
養子縁組は原則として当事者間の合意で成立しますが、要件を満たさないと民法上「無効」または「取消」し得る場合も存在します。たとえば、未成年者の養子縁組には原則として実父母の同意や家庭裁判所の許可が必要ですし、当事者に意思能力がなければ契約自体が無効とされる可能性もあります。 また、高齢者と介護者との縁組が「相続対策」を目的として行われた際、ほかの相続人から「不当な利益を得るための縁組ではないか」と疑義を持たれ、結果として縁組が無効になると、相続人としての資格が失われてしまいます。 このようなリスクを回避するには、弁護士を含む専門家に相談の上で、適切な手順での養子縁組を進めることが大切です。法的要件を確認しながら進めることで、相続時の紛争を未然に防ぐことにつながります。
7.まとめ──円滑な相続と家族関係のために早めの相談を
養子縁組は、戸籍上の扱いや相続人の範囲に影響を与える非常に重要な手続きです。特に、普通養子縁組か特別養子縁組かによって、実親との法的関係が変わるため、相続に大きな違いが生じることに注意しましょう。 また、実質的なメリットを狙って養子縁組をしても、形式が整わないと無効となるリスクや、他の相続人とのトラブルに発展する恐れもあります。
相続LOUNGEでは、弁護士をはじめとする専門家が協力し、養子縁組の相談から相続税対策、戸籍手続きまで一貫してサポートいたします。 複雑な戸籍の取り扱いや相続人の確定、さらには税務申告や名義変更の登記に至るまで、相続をワンストップで解決できる体制が整っています。スムーズかつ円満な家族関係・相続のためにも、気になる方はできるだけ早い段階でご相談ください。