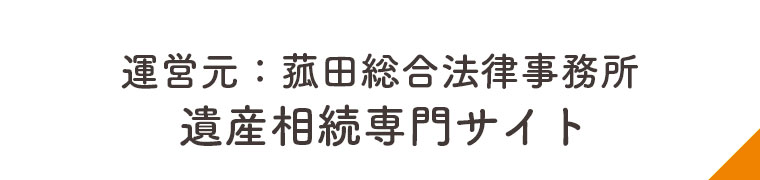会社の経営を後継者に引き継ぐ「事業承継」
- HOME
- お悩み別コラム
- 相続対策・終活・生前対策
- 会社の経営を後継者に引き継ぐ「事業承継」
動画でわかりやすく解説!
近年、中小企業の経営者の高齢化が進んでおり、2015年には経営者年齢のピークは66歳、70歳以上の年齢層が占める割合も過去最高になりました。
これから、数十万もの経営者が引退をし、事業を誰かに引き継ぐか、やむなく廃業してしまうかの選択を迫られることになります。
今回は事業承継について説明します。
1 事業承継とは
事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。
大企業では代表取締役の交代が比較的頻繁に行われ、代表取締役が代わっても会社運営が大きく変化することはほとんどありません。
一方、中小企業の場合、会社の機能のほとんどを経営者が担うことも多く、従業員や取引先も会社というよりも経営者本人を信頼している場合が少なくありません。
そのため中小企業では突然経営者が交代してしまうと、従前と同様に経営していくことが難しいことが予想されます。
事業承継には数年単位で時間が必要となるので、できるだけ早く事業承継に取り組むことが重要です。
2 事業承継の種類
事業承継は、大きく以下の3種類に分けられます。
(1) 親族内承継
経営者の子供・娘婿など、親族が後継者となるケースを親族内承継といいます。
昔から代々家業が継がれてきたように、従業員等の反発も少なく、比較的スムーズに進めやすい事業承継の方法と言えます。
ただ、親族内承継は相続問題が起こりやすい方法でもあります。経営者の財産は、大半が事業用の不動産や経営する会社の株式など、経営に関わる財産であることが多く、事業用の財産を後継者に遺すと、後継者でない子供とのバランスが崩れてしまいがちです。
親族間で将来遺産について揉めることも考えられますので、後継者とならない相続人へのフォロー等、事前にきちんと対策を取ることが不可欠です。遺留分に関しては、下記4でご説明しています。
(2) 親族外承継
会社の役員や取引先から招聘した人物に事業を承継するケースを、親族外承継といいます。
長年経営者の右腕を務めていた方が事業を承継することは珍しくなく、従業員や取引先も受け入れやすい方法です。
ただし、経営者と一従業員とでは視点や考え方が異なるため、役員に対して後継者教育を適切に行う必要があります。
また、親族内承継の場合は後継者へ株式を承継させる方法として、贈与や相続が用いられることが多いですが、親族外承継の場合は売買により行われることが多く見られます。
この場合、後継者となる従業員が株式を買い取ることができる資産を持ち合わせていないこともあるため、事業承継に向けて役員報酬を増加させ、買取資金を作ったり、借入れを行う等の工夫を計画的に行うことが重要となります。
(3) M&Aによる承継
会社を第三者に売却し、第三者が経営するケースをM&Aによる承継といいます。
親族内や会社内に適任の後継者がいない場合でも用いることができるため、後継者が見つかりにくい近年、よく用いられるようになった方法です。
売却先によっては新たな分野への進出など、会社の規模が拡大することが期待できる一方、従業員の処遇への不安などから、どうしても会社内部から反発が起こりやすい方法ではあります。
M&Aを行うにあたって、売却価格、売却先の現在の事業、従業員の処遇等、様々な条件を希望することになるでしょう。
しかし、それらを全て満たす第三者と早々にマッチングできるかどうかは分かりません。買い手を探すだけで数年単位の時間がかかることも考えられるため、早めに準備を進めることが不可欠です。
3 事業承継税制
親族内承継において、経営者から後継者に株式を異動させる方法は、①売買、②生前贈与、③遺言、④信託があります。時価より低い価額での売買や生前贈与の場合は贈与税が、遺言の場合は相続税が課税されます。
事業承継特有の税制として、非上場会社の株式等を後継者が取得した場合に課される贈与税・相続税について、以下の通り一定の要件のもとで納税を猶予する制度があります。
いずれも申請期間や申請書類等に注意が必要ですので、ご確認ください。
(1) 一般措置
後継者が相続・遺贈により非上場会社の株式を取得し、会社を経営していく場合に、納付すべき相続税のうち、非上場株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される制度です。
(2) 特例措置
10年間(平成30年1月1日から令和9年12月31日まで)の贈与・相続等を対象とした特例措置が創設されています。
特例承継計画を提出する等の条件をクリアする必要がありますが、この制度が適用されれば、100%の猶予が可能となります。
4 遺留分に関する特例
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められるもので、遺留分より少ない相続分しか得られなかった相続人は、遺留分減殺請求を行って返還を求めることができます。
遺留分の割合は、相続人が直系尊属(父母または祖父母)のみの場合は2分の1、その他の場合は2分の1で、法定相続分にこれらの割合を掛けて算出します。
したがって、後継者に財産のほとんどを承継させた場合、経営者の死後に他の相続人から遺留分減殺請求が行われ、後継者が承継した株式や事業用財産が他の相続人に散逸してしまうおそれがあります。
親族内承継を行った後にこれらの問題が起こらないよう、遺留分減殺請求権を意識した対応を生前に行うことが不可欠です。
(1) 遺留分の放棄
相続人の同意が得られれば、家庭裁判所に審判を申し立て、遺留分の放棄をしてもらうことが可能です。
(2) 遺留分に関する民法の特例
経営承継円滑化法に基づく①除外合意と②固定合意があります。
推定相続人全員の合意のもと、経済産業大臣への申請、家庭裁判所での許可を経ると以下の特例を受けることができます。
①除外合意
除外合意は、後継者が被相続人である先代経営者から贈与により取得した自社株式について、その価額を遺留分算定基礎財産に算入しないという内容を定めることをいいます。
これにより、他の相続人が後継者に遺留分減殺請求を行ったとしても、株式は対象から外すことができます。
②固定合意
遺留分の価額の算定時期は相続開始時ですが、この原則によれば、後継者が生前贈与を受けた後、自ら経営者としての努力によって株価を上昇させても、その増加分が遺留分算定基礎財産に算入されてしまいます。
そこで、後継者が先代経営者からの贈与により取得した株式について、当該合意時における価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額とする旨を合意することができます。
例えば、合意時の株式の価額が5,000万円、その後相続開始時には株式の価額が1億円に上昇している場合でも、遺留分算定基礎財産は5,000万円で計算します。
固定合意を用いることで、後継者は、遺留分の変動を憂慮することなく、経営に専念することができます。
5 まとめ
ご説明した通り、事業承継には様々な準備が必要となり、弁護士や税理士等の専門家の意見を聞きながら進めることが不可欠です。
誰しもいつ相続が発生するかは分かりませんから、事業承継の準備が早すぎるということはありません。
経営者の方は、事業承継について専門家に相談してみることをお勧めします。